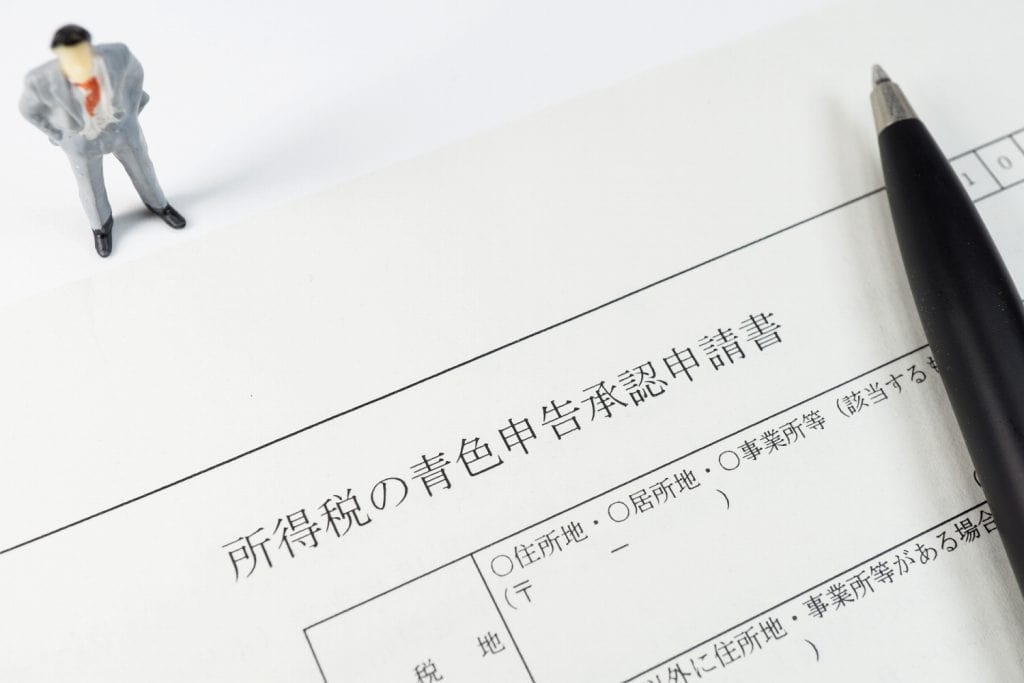個人事業主として新規開業する際に必要となるのが開業届の提出です。
開業届は税務署に提出することが義務付けられている書類であり、「出しても出さなくてもいいもの」ではありません。
この記事では、そもそも開業届とは何かといった基礎知識から、開業届を出すことのメリット・デメリットについて解説。
開業届の各項目の具体的な書き方をわかりやすく紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
- そもそも開業届とは?
- 開業届を出すメリットとは
- 開業届を出すことによるデメリットとは
- 実践!開業届の書き方・記入例
- 1.所轄の税務署名と提出日を記入
- 2.納税地を記入
- 3.納税地以外の住所地、事業所等があれば記入
- 4.氏名、生年月日を記入
- 5.個人番号を記入
- 6.職業を記入
- 7.屋号を記入
- 8.届け出の区分で「開業」に〇をつける
- 9.該当する所得の種類に〇をつける
- 10.開業日を記入する
- 11.事業所等を新増設、移転、廃止した場合
- 12.廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
- 13.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無にチェック
- 14.事業の概要を記入する
- 15.従業員を雇用する場合は、給与等の支払いの状況を記入する
- 16.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書について、該当するほうに〇をつける
- 17.従業員を雇用する場合、給与支払いを開始する年月日を記入
- 18.顧問税理士がいる場合、関与税理士を記入
- 税務署への提出方法
- まとめ
- 創業時の融資相談もBricks&UKにおまかせください!
そもそも開業届とは?

開業届とは、個人事業を開始したという事実を国に届け出る書類です。
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、所得税法第229条によって提出が義務付けられています。事業を始めれば当然「所得」を得ます。その所得(事業所得)には所得税の納税義務が発生する可能性が高いことから届出が必要とされているのです。
所得税法施行令第63条では、継続的に対価を得る行為を「事業」と規定しています。会社勤めをしながら副業としてビジネスを始める場合でも、開業届の提出は必須です。
ちなみに「個人事業の開業・廃業等届出書」は、開業時だけでなく事務所の新設や移転、廃業などの場合にも届出が必要な書類です。
開業届の提出先と提出期限

開業届は、納税地を管轄する税務署に提出します。納税地は納税者の住所と同じになるのが一般的です。
開業届の提出には期限もあり、法では事業開始から1カ月以内にすべきことになっています。
ただ、期限を過ぎて届け出をしても、もしくは開業届を出さずにいたとしても、罰則を受けることはありません。
しかし、開業すれば必要となる確定申告、これをを青色申告で行うには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。そしてこれは、開業届と一緒に出すのが一般的です。
また、自ら事業を興すような人が、法で義務付けられた手続きを「ペナルティがないなら出さない」というのでは通らないでしょう。必ず出すようにしてください。
開業届を出すメリットとは

ここまでの説明でおわかりのように、開業届は提出すべきものであり、出すことにメリットがあるから出す、という類のものではありません。
しかし、開業届を出すことで、まずは自分が事業主になった事実が公に認められることになります。会社設立とは異なり、個人事業主には開業届のみが、自身が事業主となったことの区切りになるものです。
その他にも、開業届の控えがあれば可能になることもあります。また、同時に提出するのが一般的な「青色申告承認申請書」を提出すれば、節税のメリットも受けられます。
メリットをリストにまとめると次のようなことです。
- 個人事業の屋号で銀行口座が開設できる
- 青色申告で税金の控除が受けられる
- 赤字が最長で3年まで繰り越せる
- 家族への給与を経費として扱える
- 小規模企業共済に加入できる
- 就労証明書の代わりとして使える
それぞれどういうことか説明します。
個人事業の屋号で銀行口座が開設できる

開業届の用紙には、「屋号」を書く欄があります。屋号を記入した開業届を提出しておけば、屋号を名義に入れた銀行口座が開設できます。
屋号を付けた口座を開設する際には、開業届の控えやそのコピーが必要とされるのです。
屋号が付いた名義で銀行口座を開設すれば、個人名義の口座で事業を行うよりもクライアントや取引先からの信用度が高まります。
また、銀行振込で事業関連の支払いをする際も、取引先から認識されやすくなります。
ただし、屋号だけを名義とできる銀行もあれば、屋号と本名を並べた名義のみ可能な銀行もあります。また、名義付きの口座開設を受け付けていない銀行もあります。
また、開業届の控え以外にも、事業内容や数年分の実績がわかる書類が必要となる場合があります。
青色申告で最大65万円の控除が受けられる
開業届と同時に青色申告承認申請書を提出し、青色申告をすることで税金の控除を受けることが可能です。
事業を始めると、得た所得に応じた税額を届け出る「所得税の確定申告」が必要になります。確定申告には白色申告と青色申告がありますが、国はより正確な納税額の算出のため青色申告を推奨し、控除などのメリットを設けているのです。
青色申告の特別控除では、課税の対象となる所得金額(課税所得)から最大65万円が差し引かれます。つまり結果として納めるべき税金が安くなるのです。
あわせて読みたい
最長3年まで赤字を繰り越せる
開業届を提出すれば、事業で赤字が出た場合に最長で3年まで繰り越せます。
個人事業主が支払う税額は、1年間の課税所得を元に計算されます。そのため、赤字を翌年度以降に繰り越すことで翌年度以降の課税所得が減り、節税になるのです。
例えば、ある年度の事業所得が30万円の赤字だったとします。青色申告で赤字を申告しておけば、次の年度に200万円の黒字となった場合、前年度の赤字を相殺して170万円の黒字とすることが可能です。黒字の額が少なくなれば、税金の額も少なくできます。
家族への給与を経費として扱える
開業届を提出し、青色申告を選択した場合、仕事を手伝う家族への給与を必要経費として扱うことができます。
そもそも、個人事業主の場合は、家族が従業員として働いた場合の給与を経費にすることができません。ただし、白色申告の場合は「事業専従者控除」といって一定額の控除が受けられる仕組みがあります。
一方、青色申告には「青色事業専従者給与」といって、家族が従業員として働いた期間や仕事内容によって妥当な金額を経費とすることも可能なのです。
ただし、家族への給与を経費扱いとする場合には、開業届のほかに「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要なので注意が必要です。
小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模の会社の経営者が加入できる共済制度です。この共済に加入する際、通常は確定申告書の控えが必要となりますが、開業まもなくで確定申告をしたことがなければ「開業届の控え」が必要となります。
共済制度なので、加入して掛け金を積み立てれば、廃業した際に給付金が受け取れます。
また、掛け金の全額が所得控除の対象となったり、掛け金に応じて事業資金の借り入れができたりするメリットもあります。
就労証明書の代わりとして使える

開業届の控えは、就労証明書が必要なシーンでも活用できます。
会社を辞めて個人事業主になった場合、当然ですが勤め先から就労証明書をもらうことができません。そのため、働いている事実の客観的な証明が難しくなります。
開業届を提出すると、税務署から控えがもらえます。これには税務署の印鑑が押されているので、就労証明書の代わりになるのです。就労証明書が必要な主な例として、保育園に子どもを預けるときが挙げられます。
開業届を出すことによるデメリットとは

開業届を出すと、事業を興し、それによりある程度の所得がある人だと見なされます。そのため、人によっては、開業届を出したことで次のようなデメリットが生じる可能性があります。
ただ、開業届を出すのは義務です。出さないペナルティはないにしても、出す決まりだということは認識しておいてください。
失業手当は原則として対象外

副業として開業届を出した場合、本業の会社を退職して失業保険をもらおうと考える人も多いでしょう。しかし、会社を辞めたとしても「個人事業主」としての仕事と収入があるのであれば、原則は失業保険の対象から外れます。
失業手当は、就職する意欲やその能力があるのに退職後の就労先が見つからない人に対し、その生活の保障として支給されるものです。
開業届を提出し事業を営んでいるとなれば、やるべき仕事があり、収入も見込めることになります。そのため、失業保険を受け取れない可能性が高いです。
健康保険などの扶養の対象外となる可能性がある

扶養とは、配偶者や親などから経済的なサポートを受けている状態のことです。
健康保険や厚生年金保険で被保険者の扶養家族となれば、保険料を払わなくても保険に加入できます。被保険者の側は、所得控除を受けられます。
ただし、被保険者が加入する健康保険組合によっては、個人事業主は扶養に入れない場合があるため注意が必要です。
事業所得の金額にかかわらず、開業届を出した時点で個人事業主とみなされ、健康保険の扶養から外されるかもしれません。
扶養に入っている場合、家族の健康保険組合の加入条件を確認しておきましょう。
扶養から外れた場合は、自分で国民健康保険と国民年金保険に加入し、それぞれ保険料を自己負担する必要があります。
確定申告の手続きが白色申告よりも複雑になる

開業届を出して青色申告を行う場合、白色申告よりも手続き方法が複雑になる点もデメリットです。
確定申告では、事業運営で発生した収入や支出を「帳簿」として記録し、所定の形式にまとめたものを税務署に提出する必要があります。
白色申告では、単式簿記と呼ばれる比較的簡単な方法で帳簿をつけられますが、青色申告で控除を受けるには、複式簿記による記帳が必須です。
開業届を出して青色申告をするなら、簿記に関して必要最低限の知識が必要になります。
副業していることを会社に知られる場合がある

副業をしていることを勤め先に知られたくない場合は、トラブルが起きないよう注意が必要です。
会社から給与を得ている人の税金は、基本的に会社が税額を計算し、給与から天引きされる特別徴収の形で納められています。
副業で開業届を出し、事業所得を得た場合は、全体の収入額が増えるため住民税の額も増えることになります。詳細は本人でなければ見られないようになっているケースがほとんどですが、納めるべき税額が突然増えることから、会社の経理担当者に知られる可能性もないとは言えません。
ちなみに、確定申告の際、住民税を普通徴収にするか特別徴収にするかが選択できます。普通徴収にすれば金額を知られることなく納税できますが、会社側には特別徴収から普通徴収に代わることの説明が求められるでしょう。本業分も天引きでなくなることで、手間も増えます。
副業禁止の会社であれば、副業をするべきではありません。禁止でないなら申告しておいた方がよいでしょう。
実践!開業届の書き方・記入例

ここからは、開業届の書き方について、各項目に記入する内容やポイントを解説していきます。
開業届は、最寄りの税務署で入手できます。
そのほか国税庁のWebサイトからPDFをダウンロードして印刷したものも利用可能です。
では順に見ていきましょう。

1.所轄の税務署名と提出日を記入
開業届の提出先となる税務署名と、開業届の提出日付を記入します。
各地域の所轄税務署は、国税庁のWebサイトで検索可能です。
届け出の締め切りが事業開始から1カ月であることに注意してください。
2.納税地を記入
住所地、居所地、事業所等のいずれか該当する項目に丸をつけ、郵便番号と住所、電話番号を記入しましょう。
自宅で事業を行う場合は、住所地が納税地となります。
自宅以外の場所に事業所を構えていて、事業所のある地域を納税地としたい場合は、事業所の住所を記入してください。
ただし、原則として自宅住所を納税地とするのが一般的です。
3.納税地以外の住所地、事業所等があれば記入
自宅以外にある事業所の住所を納税地の欄に記入した場合は、この項目に自宅の住所を記入しましょう。
4.氏名、生年月日を記入
個人事業を開業する本人の氏名、フリガナ、生年月日を記入し、押印しましょう。
本人印または屋号印のいずれかを使用可能です。
5.個人番号を記入
マイナンバーカードまたは通知カードにある個人番号を記入しましょう。
6.職業を記入
個人事業として営む職業を記入しましょう。
法定業種によって個人事業主税の割合が異なるため、実際の業務内容に即した職業を記入してください。
7.屋号を記入
個人事業の名称である屋号とフリガナを記入しましょう。
屋号を決めていない場合は、空欄で提出し、あとから変更することも可能です。
8.届け出の区分で「開業」に〇をつける
開業に〇をつけましょう。事業の引き継ぎを受けて開業する場合は、受けた先の住所と氏名を記入してください。
その下にある「事務所・事業所の新設・増設~」や「廃業(理由)」などの項目は、開業届の提出時に記入する必要はありません。
9.該当する所得の種類に〇をつける
事業の種類に応じて、該当する所得の種類に〇をつけましょう。
不動産事業では「不動産所得」、山林事業では「山林所得」、そのほかの一般的な事業では「事業所得」に〇をつけてください。
10.開業日を記入する
事業を開始した年月日を記入しましょう。
どの時点をもって開業とするかに特にルールはありません。
開業準備を始めた日や、開業届の提出日などを開業日として設定できます。
11.事業所等を新増設、移転、廃止した場合
開業時は該当するものがないため、空欄でOKです。
12.廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
開業する際は、この項目は空欄のままで構いません。
13.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無にチェック
開業届と同時に、青色申告承認申請書や、消費税に関する課税事業者選択届出書を提出する際は「有」に〇をつけましょう。
14.事業の概要を記入する
事業で取り扱う商品やサービス、対象となる顧客などについて具体的に記入しましょう。
15.従業員を雇用する場合は、給与等の支払いの状況を記入する
開業時点から従業員を雇用する場合は、従業員数や給与の定め方を記入しましょう。
家族を雇用する場合は「専従者」、家族以外を雇用する場合は「使用人」に区分されます。
給与の定め方には、月給や日給などの区分を記入してください。
従業員を雇用する場合は源泉徴収を行う必要があるため、「税額の有無」は「有」に〇をつけましょう。
16.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書について、該当するほうに〇をつける
従業員数が10人未満の場合、申請書を提出することで源泉所得税の支払い納期を変更できます。
開業届と同時に、この申請書を提出する場合は「有」に〇をつけましょう。
開業時に従業員を雇わない場合や、従業員に対して通常の納期で源泉所得税を支払う場合は、「無」に〇をつけてください。
17.従業員を雇用する場合、給与支払いを開始する年月日を記入
開業時に従業員を雇用する場合は、従業員への給与支払いを開始する年月日を記入しましょう。
18.顧問税理士がいる場合、関与税理士を記入
開業時点から顧問税理士がいる場合は、税理士の氏名と電話番号を記入します。
税務署への提出方法

開業届の提出先は、自宅住所の管轄税務署です。
提出先を間違えると開業手続きが遅れたり、余計な郵送コストがかかったりするのでご注意ください。
また、青色申告承認申請書などの書類を提出する場合は、開業届と一緒に提出すると効率が良いです。
営業時間内に届出をする場合

管轄税務署の営業時間内に開業届を提出する場合、記入した開業届と控え用のコピー、マイナンバーが確認できる本人確認書類、身分証明書が必要です。
また、書類の押印箇所に不備があった場合に備えて、印鑑も持参したほうが無難です。管轄税務署の受付窓口に着いたら、開業届を提出したい旨を伝えて、必要書類を渡しましょう。
記入内容について税務署職員がチェックを行い、不備がなければ提出は完了となります。
押印してもらった開業届の控えは、事業を運営するにあたって必要となる場面があるため、大切に保管してください。
毎年2月から3月ごろにかけての確定申告期間中は、税務署の受付窓口が混雑している場合があります。
確定申告期間中に税務署に行く際は、時間に余裕を持って行動することをおすすめします。
営業時間外に届出をする場合
税務署に設置されている時間外収受箱を利用すれば、土日や祝日、税務署の営業時間外でも開業届を提出できます。
時間外収受箱を利用する際は、次の必要書類を封筒に入れて提出しましょう。
- 開業届
- 開業届のコピー(控え用)
- マイナンバーが分かる書類のコピー
- 身分証明書のコピー
- 控えの返送用封筒
押印された開業届のコピーを返送してもらうため、返送先の住所を記入し、必要な金額の切手を貼った返送用封筒を同封してください。
開業届が受理されれば、後日控えが返送されます。
控えの同封を忘れてしまった場合は、税務署に保有個人情報開示請求書を送って、開業届の写しを発行してもらいましょう。
郵送で届出をする場合

開業届は郵送で提出することも可能です。
その場合は、必要書類を入れた封筒を管轄税務署の住所に送ります。
紛失などの配送トラブルを避けるため、荷物の配達状況が追跡できるサービスを利用したほうが安全です。
郵送で提出する場合、封筒に入れるものは次のものです。
- 開業届
- 開業届のコピー(控え用)
- マイナンバーが分かる書類のコピー
- 身分証明書のコピー
- 控えの返送用封筒
必要書類は、時間外収受箱を利用する場合と同じです。
開業届が受理されれば、税務署から押印済みの控えが返送されます。
まとめ

個人事業主として開業する際は、開業届の提出が必須です。
開業届を提出せずビジネスで収益を得た場合、青色申告ができず控除が受けられないといったデメリットがあるため、必ず提出しましょう。
「税理士法人Bricks&UK」では、個人事業主として開業する方に向けた支援を行っています。
創業時に必要な資金調達のサポートや、将来的に個人事業から法人へ移行する際の法人化手続き代行など、ぜひ専門家である私どもにお任せください。
事業の成功に、Bricks&UKのプロフェッショナルなサポートをご活用ください。
お問い合わせをお待ちしています。
創業時の融資相談もBricks&UKにおまかせください!
当サイトを運営する「税理士法人Bricks&UK」は、顧問契約数1700社以上、資金繰りをはじめ経営に関するコンサルティングを得意分野とする総合事務所です。
中小企業庁が認定する公的な支援機関「認定支援機関(経営革新等支援機関)」の税理士法人が、日本政策金融公庫の資金調達をサポートします。
資金調達に必要な試算表、収支計画書などを作成していきますので、資金調達のサポートと、借入後の資金繰りをしっかりと見ていくことができます。
そのため、皆様の経営の安定化に、すぐに取り掛かることができます!
まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。