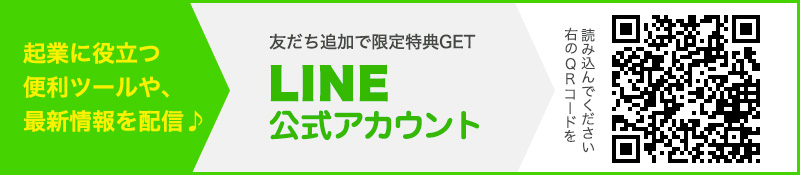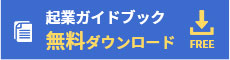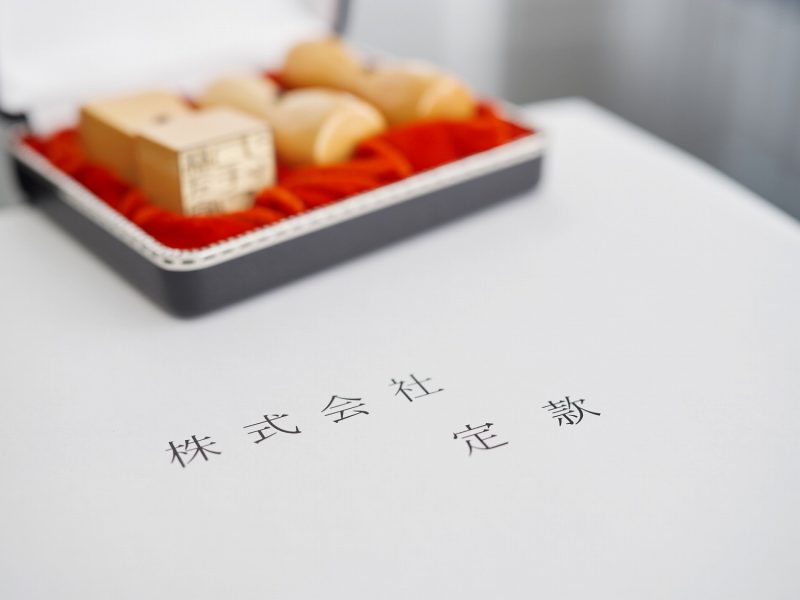
会社設立の手続きをするのに、まず行うことは会社の基本的な事項を決め、定款を作成することです。
定款には、必ず記載しなければならない事項が会社法で定められています。それが「絶対的記載事項」と呼ばれる項目です。絶対的記載事項がなければ、定款が無効となってしまいます。
さらに場合に応じて「相対的記載事項」や「任意的記載事項」も記載します。
この記事では、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項となる項目や項目例を挙げ、どのような内容にすべきかを解説していきます。

目次
必ず決めねばならない絶対的記載事項

冒頭でも触れたとおり、定款に記載する項目についてはその必要性から3つの種類に分けられます。
- 絶対的記載事項…記載がなければ定款の効力もない
- 相対的記載事項…その事項について決定した場合には記載が必要
- 任意的記載事項…定款に記載せず別でルール化してもよい
どんな会社であっても記載が義務付けられているのは絶対的記載事項です。
とはいえ、相対的記載事項とされているものの中で会社として決めた事柄があるならそれも記載しておかねばなりません。
「任意的記載事項」については記載が必須ではないものの、押さえておいた方が事業運営がスムーズになるような項目です。
記載事項3種類の概要と具体的な項目
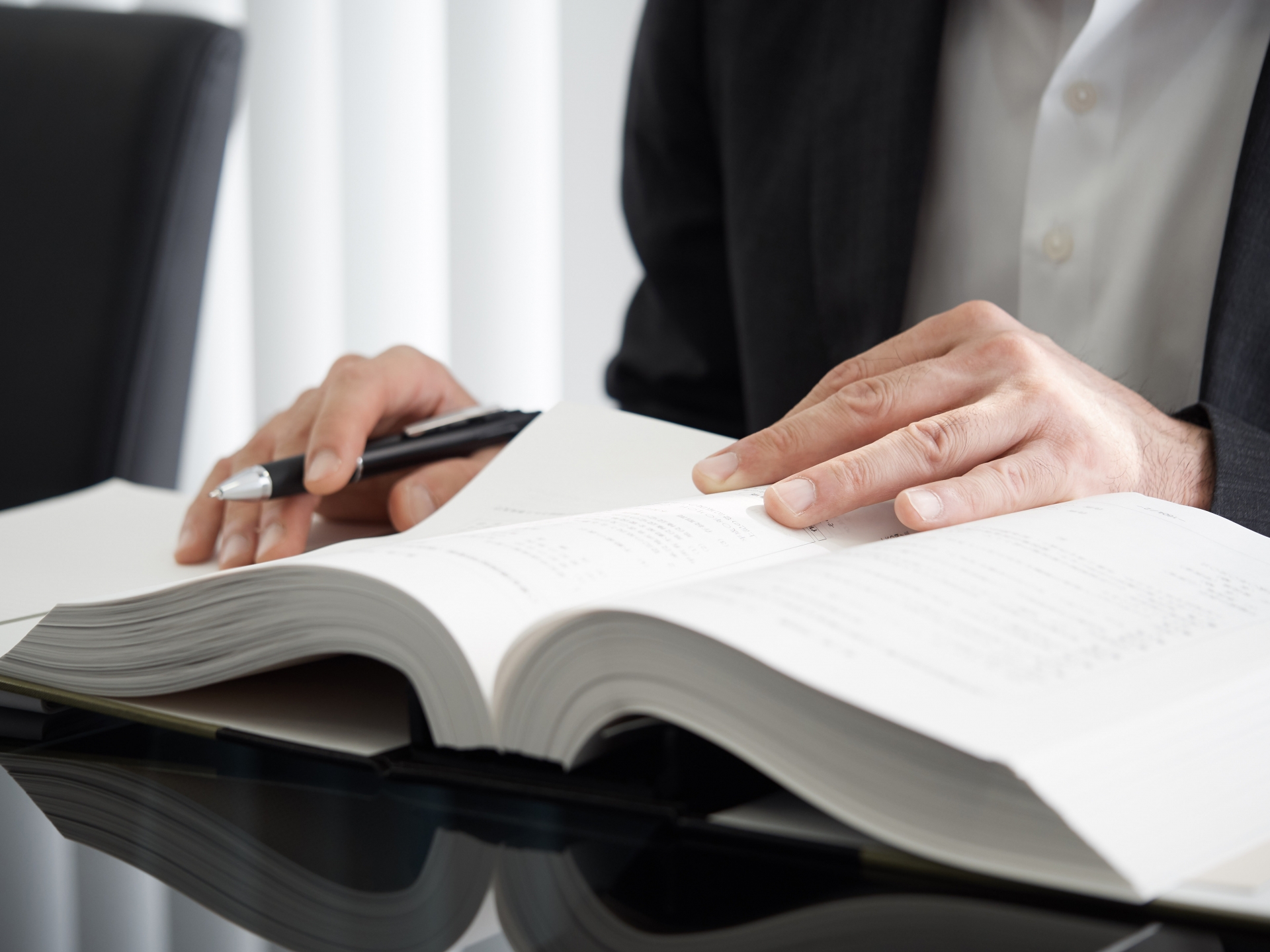
次に、上で紹介した3種類の記載事項の概要と、それぞれの具体的な項目について解説します。
絶対的記載事項の具体的な内容&書き方
絶対的記載事項とは、「法人を設立するなら絶対に決めなければならない事項」のことです。
ただし、「発行可能株式総数」については株式会社の場合のみ対象となります。
絶対的記載事項にあたるのは次の項目です。
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
- 発行可能株式総数
厳密には、最後の発行可能株式総数は会社法第27条の記載事項ではありません。しかし、設立登記までには定款に定めることが義務付けられている(会社法第37条)ので、ここで説明しておきます。 それぞれについて見ていきましょう。
事業目的
事業目的は、「事業内容」を記載します。
たとえば飲食業、会計事務所、システム開発、などと記載するので、目的というよりは事業の内容を記載する項目です。
商号
商号には「会社の名前」を記載します。また、株式会社、合同会社、など会社の種類がわかる記載も必要です。
本店所在地
「会社の住所」を記載します。
番地まで記載しても良いのですが、番地は省略可能です。最小行政区画である市町村、区まで記載すれば問題ありません。
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
「会社設立に際して出資される最低額」を記載します。会社法による制限は特にないため、自由に決定できます。
発起人の氏名または名称および住所
「発起人の名前」を記載します。
発起人の名前は個人名を記載しても法人名を記載しても問題ありません。
個人の場合は名前のみ、法人の場合は名前と住所を記載します。
発行可能株式総数
発行可能株式総数とは、「株式会社が発行することができる株式の総数」のことです。
認証を受けるだけの定款への記載義務はありませんが、設立登記前までには記載しなければならない旨が会社法で定められています。
また会社設立時には、定款で定めた発行可能株式総数の1/4以上の株式を発行する必要があります。
相対的記載事項の具体的な内容&書き方
相対的記載事項とは、「決定するのであれば定款に必ず記載しなければならない事項」のことです。
決定しても定款に記載がなければ、定款自体は有効でもその事項については効力を得ません。
また逆に言えば、決定しないなら定款に記載する必要はありません。
具体的な項目には次のような内容が挙げられます。
- 現物出資
- 財産引受
- 発起人の報酬
- 設立費用
- 株式の譲渡制限に関する定め
- 株券発行の定め
- 取締役等の任期の伸長
- 株券発行の定め
それぞれ見ていきましょう。
現物出資
株式を引き受ける場合、通常はその対価として金銭の出資を行います。
しかし発起人に限っては金銭以外の出資が許可されています。これが現物出資です。
具体的には土地や建物の出資が挙げられ、出資時にはこれらの財産を評価する必要が生じます。
財産の評価は公正に行わないと、会社か現物出資者のいずれかが不利益を被ることになります。
そこで現物出資を行う場合はその旨を定款に記載し、検査役の調査を受けることが義務付けられています。
現物出資を行う場合定款への記載は義務ですが、例外的に検査役の調査が行われない場合もあります。
具体的には、次のいずれかの条件を満たすと検査役による調査が不要です。
- 定款に記載された価額の総額が500万円を超えない
- 市場価格のある有価証券について、定款に記載された額が市場価格を超えない
- 価額が相当であることについて弁護士、公認会計士、監査法人等の証明を受けている
財産引受
財産引受とは、「発起人が会社設立に際して第三者から財産を譲り受ける契約を締結すること」です。
現物出資とは異なり、株式を対価とするわけではありません。
財産引受の場合も現物出資と同様に、定款に記載して検査役の調査を受けることが義務付けられています。
その理由は、財産を適正に評価すると同時に、現物出資の規制を避けるための隠れ蓑になるのを防止するためです。
また財産引受の場合も現物出資同様、条件を満たすと検査役の調査が不要になります。
具体的な条件も現物出資の場合と同じで、次の条件のいずれかを満たすことです。
- 定款に記載された価額の総額が500万円を超えない
- 市場価格のある有価証券について、定款に記載された額が市場価格を超えない
- 価額が相当であるとの弁護士、公認会計士、監査法人等による証明を受けている
発起人の報酬
発起人が会社から報酬を受け取る場合、公正さを保つために定款に記載し、検査役の調査を受けることが義務付けられています。
これは、報酬額が多すぎたり少なすぎたりしないようにするためです。特に発起人が相場から大きく外れた膨大な額を請求できないようにするという目的があります。
設立費用
発起人が会社設立のために使った費用は、会社に請求することが可能です。
しかし発起人に自由に請求を認めると、実際にかかった費用以上の請求を行うかもしれません。
そのため、設立費用に関しても請求があるならその旨を定款に記載し、検査役の調査を受けるよう義務付けられています。
株式の譲渡制限に関する定め
株式の譲渡制限とは、「株式の譲渡に会社の許可が必要である」ということです。
つまり、株式譲渡に会社の許可を必要としたいのであれば、それを定款に記載する必要があります。
株式の譲渡制限を行わない場合、会社は公開会社となり、役員を揃えなくてはなりません。
会社を設立してすぐに役員を揃えるのは難しいため、株式の譲渡制限に関する定めは定款に記載されるのが一般的です。
株券発行の定め
株式は電子媒体、紙媒体の両方を含む用語ですが、株券は紙媒体の株式を指します。
現代では株式は電子媒体で取り扱うのが一般的なので、基本的には株券発行する必要はありません。
あえて発行する場合は、定款に記載する必要があります。
取締役等の任期の伸長
定款に何も書かなければ、取締役など役員の任期は原則2年です。
定款に記載すれば、最大10年まで伸ばすことが可能です。
合同会社の場合はそもそも任期が定められていないので、定款に記載する必要はありません。
公告の方法
会社法上で公告することが必要な場合に、その方法を定款で指定することが可能です。
具体的には、官報、新聞、インターネットのいずれかを選択します。
ただしもっとも広く使われているのは官報であり、特別定款に記載しなければ、官報にて公告されるものと見なされます。
任意的記載事項の具体的な内容&書き方
会社が自主的に定款に追加した事項を「任意的記載事項」と呼びます。
定款に記載することで、規則としてより強い拘束力を持たせることができます。
任意的記載事項には、次のような項目が挙げられます。
- 事業年度
- 取締役等の役員の数
- 株主総会の議長
- 定時株主総会の招集時期
- 基準日
それぞれ見ていきましょう。
事業年度
事業年度とは、会社の「決算期」を指しています。
決算期は自由に決めることが可能で、それを定款に記載しておけば明確になります。
取締役等の役員の数
株式会社に必要な役員の数として、取締役会を設置していない会社は取締役が1名以上、取締役会を設置している会社では取締役が3名以上+監査役が1名以上と法で定められています。
これらは当然のこととして従った上で、役員数の下限や上限を決定することができます。
株主総会の議長
株主総会の議長が誰なのか、また議長を改めて決めるのであればその方法について、定款で定めることが可能です。
定時株主総会の招集時期
定時株主総会をいつ行うのかを、定款で定めることができます。
基本的には、毎事業年度の終了後3カ月以内とするケースが多いです。
基準日
基準日とは、株主としての権利を持つ人を限定するための特定の日付のことです。その日の時点で株主である人だけが権利を行使できることを明確にします。
というのは、株式の譲渡は基本的に自由で、制限があるのは譲渡制限の規定がある場合のみ。
譲渡による入れ替わりなどで株主としての権利を持つ人が曖昧にならないよう、基準日の時点で株主名簿に記載のある株主だけに権利を使うことを認めるのです。
まとめ

以上、法人設立時に決めなければならない定款の内訳について解説しました。
絶対的記載事項は必ず押さえる必要がありますが、相対的記載事項、任意的記載事項を含めてもそこまで項目が多いわけではありません。
ただしほとんどが後で困らないために決めておくべき事項です。慎重に考えて決めましょう。