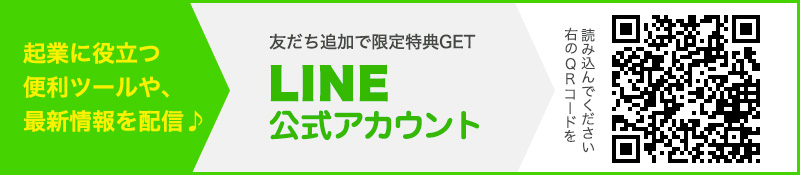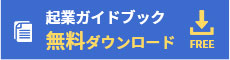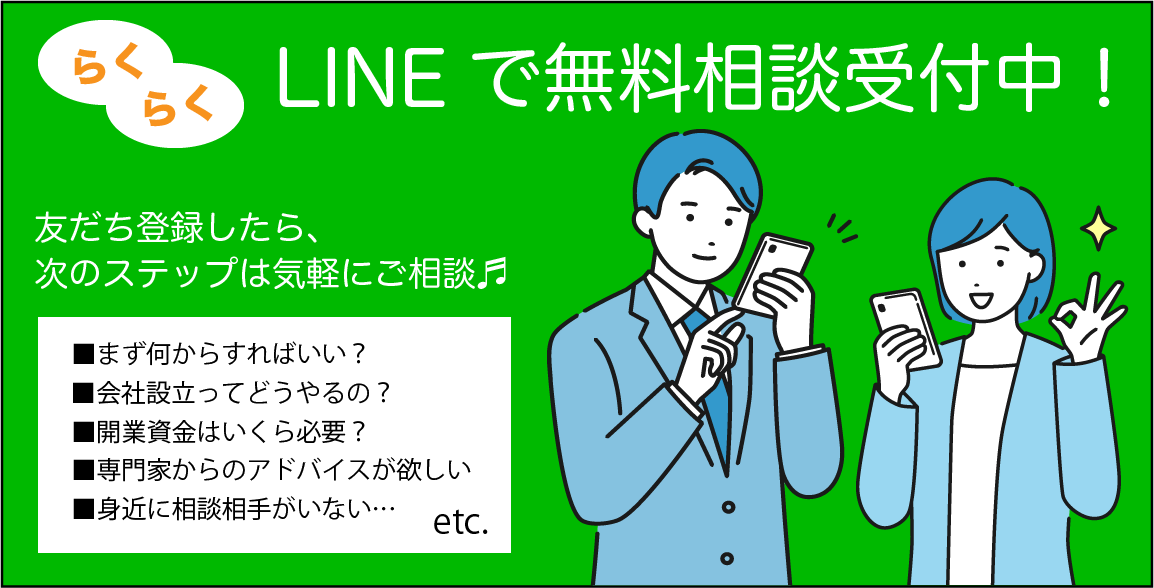株式会社を設立したら、取締役など役員にも給与(報酬)を支払うこととなります。役員報酬を経費にできることが会社設立のメリットではありますが、経費にするには条件もあります。
また、たとえ自分1人の会社であっても、好きな時に決めて好きなように支払うことはできません。
この記事では、役員報酬を経費にできる条件や決め方のルールについてわかりやすく説明していきます。注意すべきポイントも解説するので参考にしてください。

目次
役員報酬とは

役員報酬とは、文字通り役員に支払う給与のことです。会社が役員に委任した職務への対価であり、「給与」「賞与」「手当」といった名目は問わず、現金以外も該当します。
ただし、会社とは雇用関係にある従業員への給与とは、税務上の取り扱いが異なります。
従業員に支払った給与は、全額を経費として計上できます(税務上はこれを「損金に算入できる」と言います)。しかし、役員報酬は条件を満たした場合しか経費に計上することができません。
そもそも「役員」とは

役員報酬の支給対象となる「役員」には、会社法でいう「取締役」や「会計参与」、「監査役」のほか、執行役や理事、監事、清算人、そして次のようないわゆる「みなし役員」が含まれます。
- 経営に参加しているが、取締役や理事などでも従業員でもない人
- 同族会社の従業員のうち、経営に参加し、かつ持株割合が一定数を超える人
役員報酬を経費にするための条件

役員報酬を経費として計上できるのは、次の3つのいずれかに当てはまる場合のみです。
| 給与の種類 | 概要 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月一定額の報酬を支払うもの |
| 事前確定届出給与 | 定期賞与のように支給時期や金額が事前に決まっているもの |
| 業績連動給与 | 会社の業績に伴い金額が変わるもの |
定期同額給与

定期同額給与とは、毎回一定の金額を報酬として支払うものです。役員の給与は時間や日単位の対価ではないため、変動がないことが基本です。また、いわゆる月給制での同額というより、年報を12等分して支給する形が一般的です。
事前確定届出給与
「事前確定届出給与」は、従業員に対する夏季・冬季などの定期賞与のように、毎月ではないものの、あらかじめ支給する時期や金額(算定基準)が決まっているものです。
その名のとおり、事前に税務署への届出を行った上で支給することが必要です。届出をしていない場合は経費にはできません。
業績連動給与

「業績連動給与」は、利益連動給与とも呼ばれます。文字どおり業績に連動、つまり売上の上がり下がりで金額が変わるものです。
ただしこれは同族会社でないか、同族会社でない会社の完全子会社の同族会社のみに認められている役員報酬で、業務執行役員への支給に限られます。
しかし前述のように9割が同族会社の中小企業では、実質的に対象となる会社は稀でしょう。
ちなみに「業務執行役員」とは、取締役会設置会社の代表取締役または取締役のうち業務を執行する取締役として選定された人、委員会設置会社の執行役、またはそれに準じる役員をいいます。
社外取締役や監査役は業務を執行する人を監査する役割のため、該当しません。
役員と役員報酬を経費にするための条件を見たところで、次に役員報酬についてよくある疑問を解決していきましょう。
役員報酬の額はいくらでもいい?
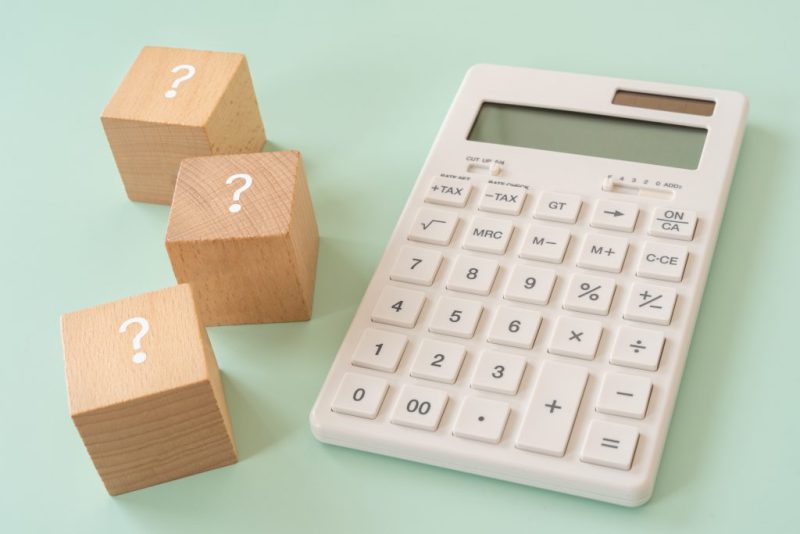
役員報酬の額について、法令などによる決まりはありません。従業員より低く設定することもできますし、何倍も高額な設定をすることもできてしまいます。
とはいえ、経費とするには報酬として妥当な金額と見なされなくてはなりません。また、役員報酬が高額となれば、個人の所得税や住民税、社会保険料もそれに伴い高くなってしまいます。あまりに低ければ、自分の生活が厳しくなります。
役員報酬の平均額はどれくらい?
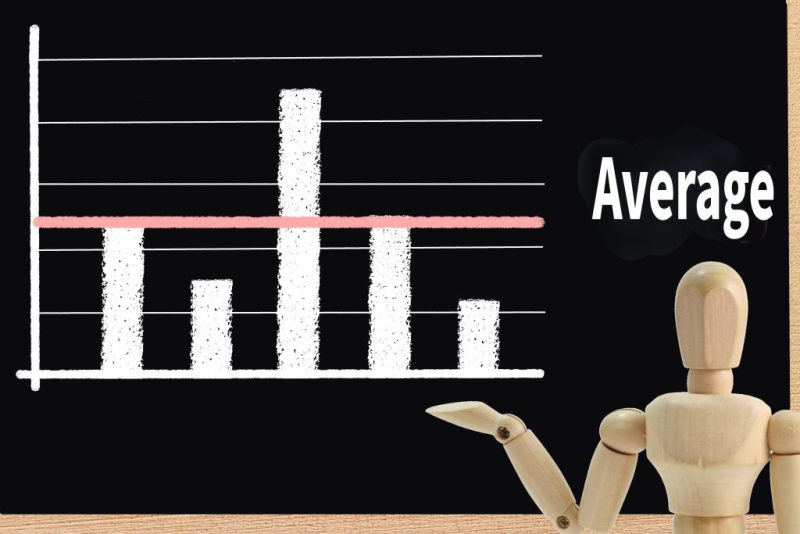
金額の参考として、役員報酬についての統計を見ておきましょう。株式会社の役員報酬の平均額を企業規模別にまとめたものです。
| 企業規模 | 令和2年分の平均 | 令和3年分の平均 |
|---|---|---|
| 資本金2000万円未満 | 約582万円 | 約615万円 |
| 資本金2000万円以上5000万円未満 | 約857万円 | 約922万円 |
| 資本金5000万円以上1億円未満 | 約1086万円 | 約826万円 |
ただしこれはあくまで「平均」なので、実際の額には個々に大きな高低差があります。自社の状況に則した額にしてください。
役員報酬の額は誰がどのように決める?

役員報酬の額に制限はありませんが、決め方には決まりがあります。
会社法では、取締役や会計参与、監査役の報酬の額や算定方法について、定款で定めるか、株主総会の決議で決めることとしています。
しかし、定款で役員報酬の額を定めている会社は中小企業などでは特に少ないという実状があります。そのため、株主総会で役員報酬の総額を決め、各人の報酬額の決定は代表取締役に一任する、というのが一般的です。
1人会社の役員報酬の決め方は?

1人会社の場合も、やるべきことは同じです。役員報酬、つまり自分の報酬は定款で定めるか、株主総会の決議で決めます。
株主総会といっても株主も自分1人なので、自分で議案を出し、自分で承認するという形式を取ります。その内容は議事録に残しておかなくてはなりません。
役員報酬は何を考慮して決める?

1人会社の場合、額をどの程度にするかについては、個人と会社、どちらの利益(節税効果)を重視するかによって変わってきます。状況に合わせて、バランスを取ることが重要です。
会社の利益を優先する場合

会社の利益を多くすれば、融資を受けようとする時に、金融機関からの印象がよくなります。経営状況が良好であれば、返済能力も高いと判断できるからです。
役員報酬を未払い計上することについては、それにより「定期同額給与」に該当するかどうかが問題となります。
例えば急な資金繰りの悪化などやむを得ない事情で一時的に未払いとするも、短期間のうちに支払う予定である場合。このようなケースでは、経費として問題ないと考えられます。
しかし、未払いの状態が長く続くようであれば、定期同額給与には当てはまらないと見なされ、税務上「損金不算入」となる可能性が高くなるので注意が必要です。
個人の利益を優先する場合

個人の所得を多くすれば、プライベートでローンを組む時などに有利になります。会社の融資と同じく、返済能力が高いと見なされるからです。
しかし前述のとおり、個人の所得が増えれば自己負担する社会保険料や所得税、住民税も高くなります。社会保険は労使折半のため、会社の負担も増えることとなります。
ちなみに、会社が負担する社会保険料の額は報酬の約15%です。
設立当初は経営の安定を優先

会社の設立当初から黒字経営となるケースは稀であり、経営が黒字になるまでには半年ほどかかるのが一般的です。経営を安定させるため、必然的に会社を優先させるケースが多いでしょう。
そのため、当面の間は役員報酬なし、もしくは低額でも生活できるだけの貯蓄をしておく必要があるのです。
経営安定後は法人税と個人税のバランスを重視

売上が伸び、所得が増えてくれば、法人税と個人の所得税のどちらの税率をとるかで節税効果が大きく変わってきます。
法人税は比例税率といって税率が約15%で固定されていますが、所得税は累進課税のため、所得が増えると税率も高くなります。事業計画、売上予測をしっかり立てて決めねばなりません。
その他、夫婦経営なら扶養に入れるかどうか、共同経営の場合は会社への貢献度など、ケースによって考慮すべき事項もあります。
役員報酬の定期同額給与の額はいつまでに決める?

しかし所得が高くなれば、税金の額も比例して高くなってしまいます。
役員報酬の額の決定は、原則として事業年度の開始日から3カ月以内にしなくてはなりません。
この期限は、前述の定期同額給与の改定について定められているものです。条件から外れれば、経費にできなくなります。
これに基づき、設立当初の役員報酬額の設定も同じく3カ月以内に行うこととされています。
役員にボーナスを支給したい場合は?

前述のように、所定の時期に決まった額の給与を支給するのが、役員報酬を損金算入できる条件の1つ「事前確定届出給与」です。
事前確定届出給与を支給する場合は、原則として次のいずれか早い日までに届け出をしておく必要があります。
- 株主総会の決議日または職務の開始日のいずれか早い日から1カ月以内
- 会計年度の開始日から4カ月以内
ただし、新設法人の設立時の役員の事前確定届出給与については、設立日から2カ月以内に届け出る決まりとなっています。
業績が良かったから急きょ今回だけ、など事前に届出をしていないものについては損金算入できません。
役員報酬はいつから支給する?

役員報酬の額を決めたら何か手続きは必要?
役員報酬は。当人が役員に就任し、役員報酬の額が決まった日から支給対象となります。そのため役員について定める株主総会の日となるのが一般的です。
報酬の額は事業年度開始日より3カ月以内に決めればよいため、経営が安定しない設立直後はあえて決めずに2カ月間0円とし、3カ月目に決めて支払う会社もあります。
支給日は、従業員のように出勤状況などから〇日締め〇日払いとする方法を取る必要はなく、〇月分を当月末日に支給するなど自由に設定できます。
3カ月を超え、例えば半年後などからの支給にすると損金算入ができなくなるので注意が必要です。
役員報酬は未払い計上できる?

役員報酬を未払いとすることについては、それにより「定期同額給与」に該当するかどうかがポイントとなります。
例えば急な資金繰りの悪化などやむを得ない事情で一時的に未払いとするも、短期間のうちに支払う予定である場合。このようなケースでは、損金として算入しても問題ないと考えられます。
しかし、未払いの状態が長く続くようであれば、定期同額給与には当てはまらないと見なされ、損金不算入となる可能性が高くなるので注意が必要です。

役員報酬の額が決まったら、5日以内に所轄の年金事務所に届け出る必要があります。
これは報酬を受け取る役員個人の社会保険(厚生年金と健康保険)への加入のための手続きです。健康保険と厚生年金は同時に手続きできます。
必要となるのは、会社が社会保険の適用事業所となることについての「新規適用届」と、役員それぞれについての「被保険者資格取得届」、役員に扶養家族がいる場合には「健康保険被扶養者届」です。添付書類として、登記簿謄本も提出します。
ちなみに、役員は労働保険(雇用保険および労災保険)の被保険者とはなりません。ただし、使用人兼務役員であれば対象となります。
役員報酬の額を年度の途中などに変更することについて

上の章にもあるように、役員報酬の額は事業年度開始より3カ月以内に決めることで経費としての計上が可能になります。
それを過ぎてから変更する場合はどうなるのかについても見ておきましょう。
事業年度開始3カ月より後に報酬額を変更すると…

期限より後に変更すると定期同額給与とは見なされなくなるため、損金算入できなくなります。とはいえ、金額を変更すること自体は可能です。
例えば事業年度開始から半年後に役員報酬を増額した場合、増額分については損金にはできません。また、減額した場合は、減額後の金額だけを損金に算入できます。
変更には臨時株主総会や取締役会などでの決議が必要なこと、議事録に残さなくてはならないことも忘れてはいけません。
期限を過ぎても経費にできる例外もある

役員報酬の額の変更は、正当な事情あるいはやむを得ない理由と判断されるものについては、例外的に期限後でも損金算入が可能です。例外として認められるのは、変更の理由が次のいずれかに当てはまる場合です。
- 臨時改定事由
- 業績悪化改定事由
それぞれどういうケースか見ていきましょう。
臨時改定事由
臨時改定事由には、社長から会長、従業員から役員といった地位の変更をする場合や、職務の変更に伴い職責の重さが大きく変わる場合などが該当します。増額する場合も減額する場合も対象です。
ただし、肩書だけが変わり職務内容に変更がないなどの場合には認められません。
業績悪化改定事由
業績悪化改定事由には、例えば融資の返済計画に見直しが必要となったり、不特定多数の株主がいる会社で責任を問われたりするような業績悪化が該当します。この場合は当然ながら、減額のみが対象です。
単に「予想より悪化した」というのではなく、第三者にも影響する客観的事実がなくてはなりません。
例外的理由による役員報酬変更の期限

事前確定届出給与について上記の変更をする場合、経費計上するためには変更にも届出の期限があるので注意が必要です。
- 臨時改定事由については、その事由が発生した日から1カ月以内
- 績悪化による場合は、原則として変更の決議をした日から1カ月以内
役員の退職による職制の変更などの場合は、その原因となる退職日から1カ月以内の届出が必要です。
業績悪化による場合は、原則として報酬変更の決議をした日から1カ月以内に届け出なくてはなりません。
事前確定届出給与の届出先は、所轄の税務署です。
役員報酬について知っておきたい注意点

最後に、役員報酬について注意すべきことをまとめて紹介します。
役員報酬は日割り計算できない

月の途中で会社を設立したり、役員が就任・退任したりするケースもあるでしょう。しかしその場合、役員報酬を日割り計算して払うと損金にはできません。
そもそも役員報酬は従業員の給与のような「日々の労働の対価」ではないため、日割りという概念がありません。また、日割り計算によって金額が「定期同額」でなくなるため、役員給与を損金算入できる要件から外れてしまいます。
設立後、半月分など日割りの額で計算して役員報酬を支払った場合には、その後の月もそれと同額までしか損金算入できなくなるので要注意です。
使用人兼務役員の扱いに注意が必要

取締役などの役員であっても、支店長や営業所長、部長や課長といった役職につくケースはよくあります。役員でありながら従業員としても部門長などの肩書を持ち、他の従業員と同じように常勤で働く場合には、使用人兼務役員として見なされます。
使用人兼務役員の給与は、役員としての給与部分は役員報酬となりますが、従業員(使用人)としての部分は役員報酬のルールに縛られず損金算入が可能です。
しかし、使用人兼務役員とは見なされないケースに注意が必要です。代表取締役、専務や常務取締役などのほか、非常勤だったりみなし役員であったりする場合は使用人兼務役員にはなれません。
また、使用人兼務役員として支給する額の合計(つまり使用人としての給与を含む額)が、職務などに照らして不相応に高額だと見なされた場合にも、損金算入は認められないので注意が必要です。
損金(経費)にできないケースをおさらい
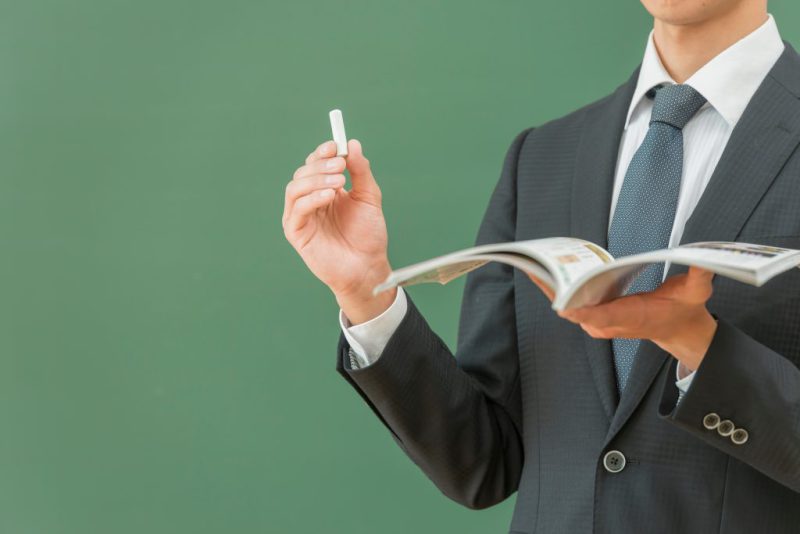
役員報酬は、その額や決定時期に決まりはないものの、損金算入(経費計上)ができるかどうかが会社経営に大きく影響します。
前提として役員報酬は損金不算入であるものの、損金にできる場合があります。ここではわかりやすく、損金算入不可となる主なケースを改めて見ておきましょう。
- 事業年度開始から3カ月より後に決めた役員報酬
- 定期同額でない突発的な報酬
- 非同族会社の完全子会社でない同族会社の業績連動給与
- 期中に金額を変えた場合の差額
- 期限までに届出をしていない事前確定届出給
- 期限までに変更の届出をしていない変更分の差額
やむを得ない事情があると税務署に見なされた場合には損金算入可能な場合もありますが、基本的にはできないと考えておかなくてはなりません。
損金算入の可否を自己判断するのは危険

役員報酬については、法人税額を下げるための利益操作に使われる例もあることから、さまざまな条件や期限が設けられています。
役員報酬について取り決めや変更をしたものの、定期同額給与や事前確定給与などの条件に該当しないと判断されれば、損益不算入となります。
そうなると、税額が増えるだけでなく、延滞税などが発生する恐れもあるため、専門家に相談することをおすすめします。
役員報酬の決め方
役員報酬はルールを守って有益に

役員報酬を損金に算入できれば、大幅な節税が可能です。しかし、損金算入するにはいくつかのルールを守らなくてはなりません。
役員報酬の決定は株主総会で決めるのが一般的で、変更するにも条件や期限があります。一方で、期限があるとはいっても例外で認められる場合もあり、損金算入の可否を自分で決めるのは難しいでしょう。
そのため、役員報酬の額を決める場合や変更しなければならない場合などには、早めに専門家である税理士に相談することをおすすめします。
当サイトを運営する「税理士法人Bricks&UK」では、クライアント各社の事情を踏まえた税務相談が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。