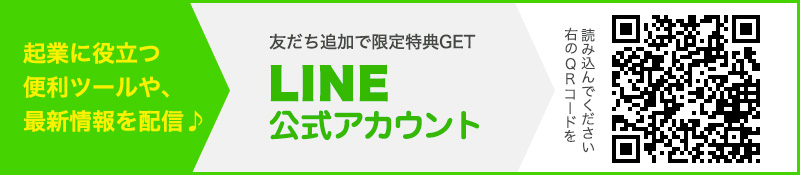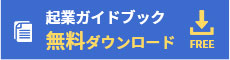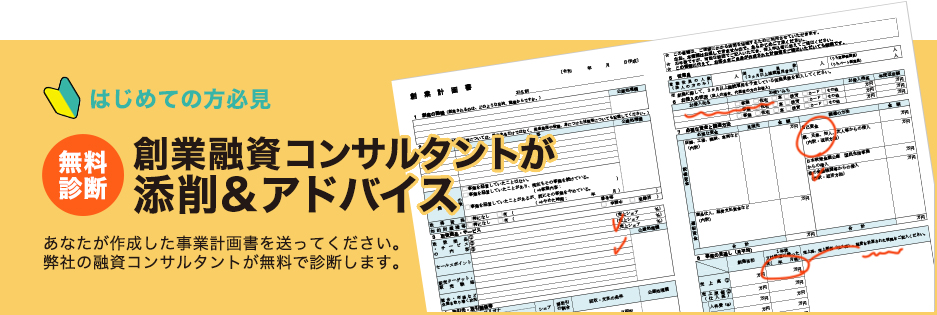創業融資を受けるのに欠かせない創業計画書には、経営者の略歴を書く欄があります。
始めようとする事業と同じ業種の経験が一定以上あれば、自己資金要件を満たせることもある経営者の略歴。ぜひ、ポイントを押さえて最大限にアピールしたいものです。
この記事では、「経営者の略歴等」の部分にフォーカスを当てて解説していきます。ぜひ参考にしてください。
目次
「経営者の略歴等」記入の5つのポイント
「経営者の略歴等」の欄は、次のようなポイントを押さえて記入することで効果的なアピールができます。
- 事業に直結する経歴を書く
- 経験で得た資格やスキルも書く
- 同業者でなくてもわかる説明にする
- 年数や役職、束ねた人数など具体的に書く
- 未経験なら共通点を探して書く
事業に直結する経歴を書く
経営者がどのような経歴を持つかは、事業経営の成功にも大きく影響すると考えられています。
融資では自己資金が必須ですが、日本政策金融公庫の創業融資では同業種での経験が一定期間以上あれば自己資金要件を満たしたと認められることもあります。
そのため、アルバイト経験や転職経験など多くの業種の経験があっても、始める事業に直結する経験を優先的に書いてください。
経験で得た資格やスキルも書く
経歴だけでなく、その経験で得た資格やスキルも書きましょう。これも、事業に直結するスキルを優先にしてください。
何をして何を得たのか、自分ならではの視点で得たノウハウなども書くとよいでしょう。
事業と結びつかない資格やスキルを書く必要はありません。
同業者でなくてもわかるように説明する
融資担当者は、あらゆる業種の事業主と接しており、ある程度の知識も有していると考えてよいでしょう。
とはいえ、専門用語を多用することは避けてください。
例えばITスキルをアピールするなら、 フレームワークや実行環境の経験より、「通販サイトの設計・プログラミングを経験した」といった書き方の方がわかりやすいです。
年数や役職、束ねた人数など具体的に書く
経験やスキルを書く際、単に「○○の業務に従事した」といった書き方だと抽象的で伝わりません。
面談に質問の手間にもなるので、はじめから書いておきましょう。
「○○の業務に〇年間従事し、○○(役職名)として○○人の部下を率いていた」といったように、数字や具体的な役職、業務内容を書いてください。
未経験なら共通点を探して書く
中には、未経験の業種で事業を始めようとする人もいるでしょう。正直なところ未経験の分野での起業には、融資のハードルは高くなります。
よほど急ぐ事情がなければ、ある程度の経験を積んでから融資の申し込みをする方が断然有利です。
未経験の分野で事業を始めても大きな問題とならないのは、業種経験のある人物との共同経営を行うといったケースでしょう。
それでも未経験で1人で事業を始めたいという場合は、これまでの経験や持っているスキルと、始めたい事業との共通点を見つけて書いてください。
管理職としてのマネジメント経験や営業経験などは、どの業種でも役立つものと考えられます。
まとめ

経験、スキル、失敗談、エピソード、感情、などアピールすべきポイントは多いです。
そしてこれらを、担当者に伝わるように説明する必要があります。
いずれにしても融資にプラスになること、つまり事業にプラスになることを含めなければなりません。
事業にプラスにならなければ、上記のどれも創業計画書に入れる価値はなく、創業計画書の限りあるスペースを無駄にすることになります。
そのため、まずは大前提として必ず事業にプラスになることのみを書く、という認識が重要と言えます。
創業時の融資相談もBricks&UKにおまかせください!
当サイトを運営する「税理士法人Bricks&UK」は、顧問契約数1700社以上、資金繰りをはじめ経営に関するコンサルティングを得意分野とする総合事務所です。
中小企業庁が認定する公的な支援機関「認定支援機関(経営革新等支援機関)」の税理士法人が、日本政策金融公庫の資金調達をサポートします。
資金調達に必要な試算表、収支計画書などを作成していきますので、資金調達のサポートと、借入後の資金繰りをしっかりと見ていくことができます。
そのため、皆様の経営の安定化に、すぐに取り掛かることができます!
まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。