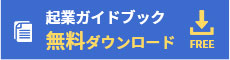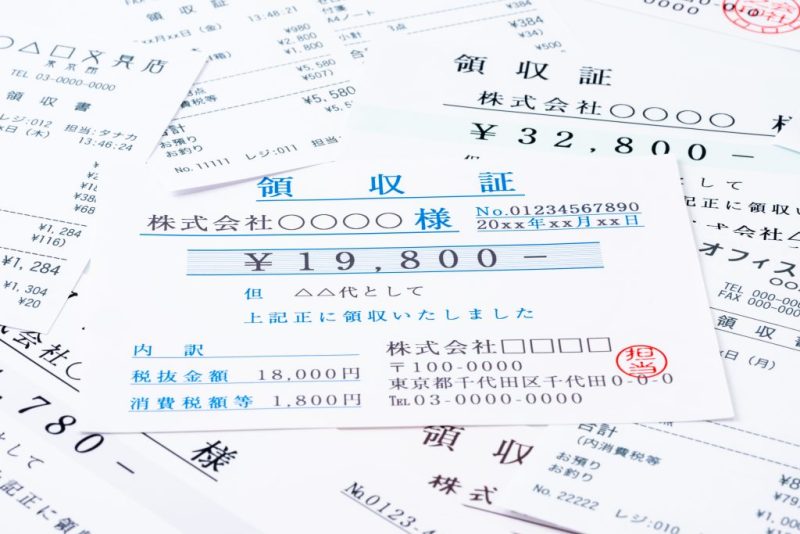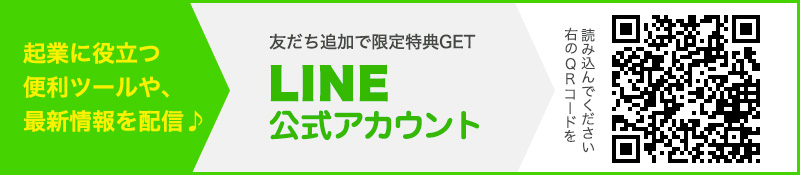会社を設立するには、資本金のほかに、登記などの手続きのための法定費用がかかります。その金額は、資本金100万円未満の株式会社で約23万円、合同会社で約10万円です。
法律上、株式会社の設立は資本金がたとえ1円でもできる形となってはいますが、1円では会社は設立できません。
この記事では、会社設立にかかる費用とその内訳を具体的に見ていきましょう。
節約する方法や、会社設立を自分でする場合と専門家に依頼する場合との違いも解説します。

目次
会社設立にかかる費用と内訳
まず、会社設立時に必要となるお金について、法人設立の法的な手続きにかかるお金と、それ以外とに分けて見ていきます。
設立手続きにかかる費用

株式会社を設立するにあたって必要となる法的手続きは、「定款を作り、公証人による認証を受けて、法務局に登記をする」というものです。
定款を紙で作成し、発起人自身が手続きする場合に必要な費用を見てみましょう。
| 費用の項目 | 金額 |
|---|---|
| 紙の定款認証時に貼る収入印紙代 | 4万円 ※電子定款の場合は不要 |
| 公証役場での定款認証手数料 | 資本金100万円未満:3万円 資本金100万円以上300万円未満:4万円 資本金300万円以上:5万円 ※合同会社の場合は不要 |
| 定款の謄本取得費用 (登記申請用) | 約2,000円 (ページ数により異なる/用紙1枚につき250円) ※電子定款の場合、1件700円+用紙1枚につき20円 |
| 【電子定款の場合】 電磁的記録の保存 | 1件につき300円 ※紙の定款の場合は不要 |
| 登記申請に必要な登録免許税 | 15万円~ ※合同会社の場合は6万円~ |
| 代表者印の作成費用 | 4,000円~ |
| 印鑑登録証明書(個人)の交付手数料 | 600円~(1通300円) ※定款認証時、登記申請時の両方で必要 ※定款認証時は発起人全員分、登記申請時は取締役分 |
| 合計 | 法定費用 株式会社:約23~25万円 ※電子定款の場合は-4万円 合同会社:約10万円 その他 印鑑作成費用等:約4,600円~ |
株式会社設立時の登録免許税の額は、「資本金の1000分の7」もしくは15万円の「どちらか高い方」です。そのため、最低でも15万円となります。
このように、株式会社の設立には少なくとも23~25万円程度が必要です。ただし具体的な金額は、資本金の額や発起人の人数、定款の枚数や購入する印鑑の額などによって異なります。
会社用印鑑の額はピンキリ

代表者印は、会社のいわゆる実印と呼ばれるもので、「○○株式会社代表取締役印」などと彫られたものです。印影の形から、丸印とも呼ばれます。
この他、金融機関の口座に使う銀行印、請求書など日常で使う角印や認印をセットで作っておくのが一般的です。
3~4本セットで、4,000円ほどの比較的安価なものから、材質や運気にこだわった15万円以上のものまでピンキリです。
電子定款なら印紙税が不要
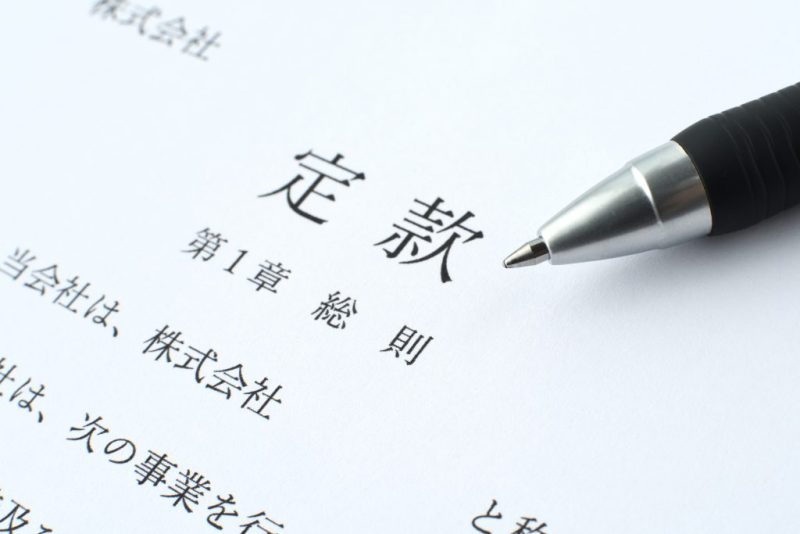
定款認証の際、紙の定款には印紙税がかかるため、4万円分の収入印紙を買って貼付する必要があります。
しかし定款は、PDFで保存した電子定款でも正式に認められます。電子定款であれば、紙ではないため印紙税がかかりません。
また、謄本(電子定款の同一情報)を取得するための費用も、1件につき700円+紙1枚につき20円となり、紙より安く抑えられる可能性も高いです。

ただし、電子定款には電子署名をしなくてはなりません。そのためには、電子証明書付きのマイナンバーカードや署名用の有料ソフトウェア(Adobe Acrobatなど)、ICカードリーダライタなども必要です。
これらの用意が整っていて、ネットやPC操作に詳しい人なら、電子定款で作成・認証の手続きを取った方が安く済みます。
そうでない場合は、購入品によって印紙代4万円を超えるケースもあるので要注意です。
設立後に必要となる謄本や印鑑証明取得の手数料
会社設立が済んだ後にも、履歴事項全部証明書(以下 登記簿謄本)や印鑑証明書の添付が必要とされる手続きがあります。
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本):1通600円
- 法人の印鑑証明書:1通450円
それぞれ数百円ではありますが、複数枚が必要となるので頭に入れておきたいところです。
事業内容などによっても異なりますが、たとえば次のような場面で必要となります。
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入(適用届)
- 従業員を雇う場合の労働保険(労災保険・雇用保険)への加入
- 会社の銀行口座(法人口座)の開設
- 金融機関への融資申し込み
- 事業に必要な許認可の申請
- オフィスの賃貸借契約
また、決算時には税務申告の際に、税理士から提出を求められます。そのほか、登記内容に変更が生じた際の変更登記、オフィス移転をした場合の各種保険手続きなどでも必要となります。
そのほか事業の開始に必要な費用
法的な手続きで必要となる以外にも、事業を始めるにはさまざまな費用がかかります。
2022年度の調査によれば、開業時に要した費用の平均値は1077万円、中央値は550万円でした。しかし、250万円未満での開業も増加傾向にあります(日本政策金融公庫「2022年度新規開業実態調査」より)。
必要となる費用は、事業内容や形態などによって大きく異なります。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| オフィスの物件取得費 | 敷金・礼金・仲介手数料・前払い家賃・保険料など |
| 内装工事費 | 天井や床、壁などの仕上げ |
| 環境設備費 | インターネット環境、電気、ガス、水道設備など |
| オフィス設備・什器の導入費 | インターネット環境、PC、ソフト、電話、プリンター複合機、デスク、チェア、応接セット、キャビネットなど |
| その他消耗品の購入費 | 社名入り封筒、コピー用紙、トナー、文房具など |
| 広告宣伝費 | ホームページの制作委託、名刺作成など |
費用が特に高額になるのは、物件取得費と内装工事です。物件取得費用は、家賃の約5・6カ月分以上は見ておく必要があります。
大がかりな機械設備などの必要な事業であれば、開業費用はより高額になります。
たとえば、一人会社で自宅兼事務所での会社設立、業務もスマホとPC1台でできるなら、物件取得費も内装工事も不要で、かなり安く抑えられるでしょう。
会社設立は自分でした方が安くてお得?
株式会社の設立費用は、定款認証や登記申請など、手続きをするだけでも25万円ほどかかります。
「専門家に頼んだら報酬も必要だから費用がかさんでもったいない」と思う人も多いでしょう。しかし、自分でした方が安くて得をするとは限りません。
費用対効果を考えれば、むしろ専門家に依頼した方が得だとも言えます。まずは単純な金額の比較から見ていきましょう。
専門家に依頼した場合との比較
会社設立を自分で行う場合と、専門家に依頼した場合とで比較してみましょう。
| 項目 | 自分 | 専門家 |
| 定款認証の印紙代 | 4万円 (紙の場合) | 0円 (電子定款の場合) |
| 定款認証の手数料 | 資本金により3~5万円 | 資本金により3~5万円 |
| 電磁的記録の保存手数料 | ― | 1件300円 |
| 定款の謄本取得費用 | 約2000円~ | 約900円~ |
| 専門家への報酬 | ― | 4万円~15万円 |
大きく差が出るのは、定款認証の印紙代と、専門家への報酬です。
定款認証を自分でする場合は、印紙代の4万円が必要です。電子定款にすれば印紙代は不要ですが、前述のようにソフトウェアなどの代金がかかります。
専門家に依頼した場合は、ほとんどが電子定款となるため、印紙代は不要です。しかし、専門家への報酬は、どこに依頼するかによって金額が大きく異なります。
報酬が4万円のところに依頼すれば、自分で行うのとほぼ同じになります。10万円のところに依頼すると、6万円くらいが多くかかる計算です。
ただ、額面だけで損得は決められません。自分で行う場合と専門家に依頼する場合、それぞれのメリット・デメリットも考慮して決める必要があります。
自分で行うメリット・デメリット

会社設立の手続きを自分で行うことには、次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
- 専門家への報酬支払いが不要
- 会社法などの知識が得られる
- 会社設立の実務経験が得られる
専門家への報酬は数万円単位であり、報酬支払いが不要なのは大きなメリットです。また、自分で手続きをすれば、必然的に知識と経験が得られます。
デメリット
- 必要な手続きや調べものに時間がかかる
- 定款作成や手続きに抜けやモレが生じる可能性が高い
- 作業や行動の効率が悪く、遠回りとなるおそれがある
手続きのすべてを自分で行うには、定款の作成から認証の申請、設立登記の申請まで、いずれも難易度の高い手続きです。事業スタート時の忙しい時期に、時間と手間がかかります。
勝手がわからないので、1つ1つ調べながらとなると、情報の正誤や新旧に惑わされたり、もれやヌケでやり直しになったりすることも十分にあり得ます。
専門家に依頼するメリット・デメリット

会社設立の手続きを専門家に依頼するメリット・デメリットは、次のようなことです。
メリット
- 時間も手間もかからない
- 正確な手続きがスムーズにできる
- 知識不足によるリスクやロスを防げる
- ほとんどが電子定款に対応している
専門家に依頼する最大のメリットは、手続きに時間や手間をかけることなく本業に集中できるということです。しかも手続きは正確に、スムーズに進められます。
また、専門家ならではの知識や経験で、余計な手間が省けたり、税金の節約ができたりする可能性もあります。
電子定款にするにも、専門家ならすでに別の顧客に要したソフトウェアやIDカードリーダライタなど必要な環境は整っていることも多いです。自分では何も買う必要がないので、印紙代の実費4万円をまるごと節約できます。
デメリット
- 報酬の支払いが必須
- 手続きにかかる知識や経験が得られない
- 営業時間外の連絡ができない
専門家への依頼では、やはり報酬の支払いが大きなネックとなります。
数万円単位のお金が出ていくとなれば、しかも手続きは自分でもできるかもしれないのに…と考えると、惜しいと思うかもしれません。
その他のデメリットには、自分に知識が残らないこと、営業時間外に連絡が取れないことが挙げられます。
会社設立の手続きを代行する専門家
会社設立の手続きに関しては、次のような専門家が存在します。ただし業務範囲は資格によって限られているため、頼みたい手続きによって依頼できる先も異なります。
司法書士

司法書士は、司法に関する登記の専門家です。会社設立に関する手続きの全般(書類作成や定款認証、登記申請の手続き)を依頼することができます。
行政書士

行政書士は、行政に関する書類作成の専門家です。会社設立では、定款の作成や認証申請を依頼できます。
また、飲食店の営業許可や消防署・警察署への届出など、各種の許認可の申請も代行してくれます。
ただし登記にかかる書類作成や申請手続きは司法書士でなくてはできません。提携の司法書士を紹介してもらうか、自分で行う必要があります。
税理士

税理士は、税務・会計の専門家です。税理士資格だけでは定款認証や登記申請はできませんが、税理士は行政書士会に登録すれば行政書士業務を行うことが可能。登録している税理士なら定款の作成や認証手続きを依頼できます。
登録していない場合でも、多くの場合、司法書士と連携して会社設立を請け負っています。
また、税理士は、定款の記載内容や役員報酬など、会社設立時に決める事柄について税務の面からのアドバイスができます。知らずに多額の税金を払う事態も避けられます。
会社にとって税理士は欠かせない存在なので、早いうちから探しておくのが得策です。
税理士との顧問契約料はどれくらい?

個人事業主から法人となれば、法人税の支払いなどが必要となります。設立後の会計・税務などに税理士のサポートを受けるため、たいていの会社が税理士との顧問契約を結んでいます。
気になる報酬については、金額が自由に設定できるため依頼先によってさまざま。目安としては次の表のとおりです。