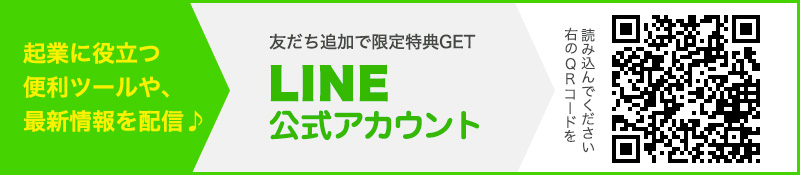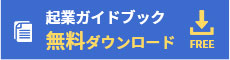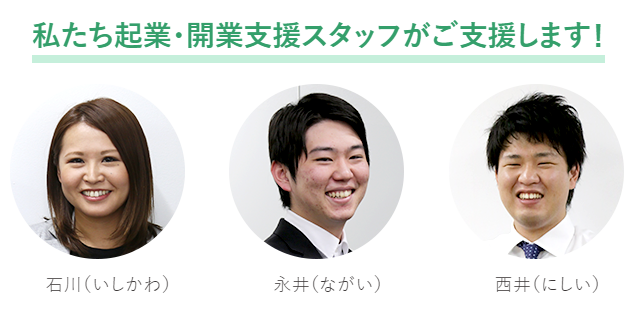個人事業主として独立し、自分のサロンを開けば、オーナーとして自由に理想通りの店づくりを行うことができます。
しかし、それまで店でやってくれていたさまざまな作業や手続きも、自分でしなくてはなりません。
この記事では、美容師が個人事業主として独立する場合の働き方の選択肢から、必要な手続き、注意点を解説します。節税方法や成功ポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
個人事業主の美容師とは

まずは、美容師が「個人事業主になる」とはどういうことかをおさらいしましょう。
個人事業主とは、会社などに雇われるのではなく、自らが事業を行う人のこと。美容師の場合は、サロン勤務でなく、独立して働く美容師をいいます。
通常のサロン勤務との違い
サロン勤務の従業員の場合、サロン店舗(会社)と雇用契約(労働契約とほぼ同義)を結んで働くのが一般的です。それに伴い、次のような違いがあります。
働き方
サロン勤務の場合、事業主(経営者)の方針に従い、就業規則など決められたルールに従って働きます。
個人事業主は、誰かに指図されることなく自分の裁量で働けます。ただし当然、社会的な法令遵守は必須です。
給与所得と事業所得
サロン勤務では、労働の対価として給与を受け取ります(給与所得)。給与には、勤務時間や能力による給料のほか、各種の手当も含まれます。支給時は、社会保険料などを天引きした後の額で支払われます。
個人事業主には、「給料」や「給与」という概念がありません。事業で得た収入から経費を引いたお金が、自分の所得となります。事業で得た所得なので「事業所得」と呼びます。
勤務時間・各種手当
サロン勤務の場合、勤務時間は労働法で限度が決められています。時間外労働・休日・深夜手当の支払いは、雇い主側の義務です。
ちなみに、役職手当や住宅手当、交通費や退職金などは、雇い主の義務ではなく任意です。
個人事業主には、労働法は適用されません。1日何時間働くかも自分の裁量です。勤務時間が週手当や退職金という概念も存在しません。
勤務時間中の保障
サロン勤務の場合は、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入も義務です。業務中のケガや失業で保障が受けられます。保険料は、雇用保険のみ一部を負担します。
フルタイム相当の時間で勤務しているなら、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入も義務付けられています。保険料は、雇い主と半分ずつ負担します。
個人事業主の場合、労働保険は対象外です。社会保険は、健康保険は国民健康保険、年金は厚生年金でなく国民年金への加入義務があります。いずれも、保障の手厚さでやや劣ります。
「フリーランス美容師」との違い
「フリーランス」とは、働き方に視点を置いた言葉です。誰にも雇用されず働く人を指します。「個人事業主」と似ていますが、まったく同じではありません。
美容師であれば、店舗を構えず面貸しなどでフットワーク軽く活躍する人のほか、自分が経営する店で美容師として活躍する人も「個人事業主」です。
働き方を限定されない美容師が「フリーランス美容師」なので、常時自分の店舗で働く人は「フリーランス」ではありません。
個人事業主となった美容師の6つの働き方

「美容師の個人事業主」といっても、一般企業のサラリーマンと同じように働き方は多様化しています。現在は7つの選択肢があります。
- 個人でサロンを経営
- フランチャイズに加盟
- 業務委託契約を締結
- 「面貸し」を利用
- シェアサロンを利用
- モール型サロンに入居
それぞれ見ていきましょう。
個人でサロンを経営
まずイメージするのは、サロンから独立して自分のお店を開くことです。
店名からインテリア、使用する機器や薬剤、BGMまですべて自分の理想のサロンを作ることができます。
ただし、一から店を立ち上げるには物件の取得費用や内外装工事が必須。多額の資金を必要とします。
フランチャイズに加盟
既存のフランチャイズに加盟する方法もあります。フランチャイズ本部のブランドや知名度、確立された経営ノウハウを学ぶなどして、サロン経営を始めます。
個人事業主にとって大きなハードルとなるのが、経営の知識不足や集客です。フランチャイズなら、その点を大きくカバーできます。
ただし、本部への加盟金やロイヤリティなどの支払いは必須です。また、自分のお店としての自由度は低くなります。
「のれん分け」と称するサポート制度を持つサロンもあります。
業務委託契約を締結
サロンから業務委託を受けるのも1つの方法です。雇用契約ではありませんが、サロンの方針に沿って美容師としての業務を行い、対価を受け取ります。
業務委託にも複数の形があり、もともと働いていたサロンで、雇用契約から業務委託契約に転換する人もいれば、まったく別の店舗と業務委託契約を結ぶ人もいます。
1つのサロンとの契約のほか、複数のサロンとの契約も可能です。
常用雇用の美容師がいない、「業務委託サロン」と呼ばれるフリーランス美容師だけのサロンも存在します。
「面貸し」を利用
美容師は、いわゆる「面貸し」(ミラーレンタル)で活躍する人も数多くいます。既存店舗の空きスペースを借りるので、資金をかなり抑えた独立が可能です。
予約の入ったときだけ働ける分、時間の自由度は高いです、しかし新たな顧客の獲得はしにくいので、固定客を確保してからの独立が必須です。
サロンへの支払いは、時間貸しや売上歩合など、サロンによって異なります。
シェアサロンを利用
地域によっては、フリーで活躍する美容師専用のシェアサロンも存在します。設備の揃ったレンタルサロンスペースを、他のフリーランス美容師たちと共有する形です。
シェアサロンも、店舗や設備などが揃っており、費用が抑えられます。
レンタル料の設定は、時間や月ごと、スポット(都度)払い、時間+歩合などさまざまです。
モール型サロンに入居
モール型サロンは、近年生まれた新しい形態のサロンです。
イメージは、ビルの入居テナントがすべて美容院である、という状態。個室のサロンスペースが並び、それぞれのテナントで、異なるフリーランス美容師が自分のサロンを運営します。
料金は、テナントと同じく物件のオーナーに賃貸料を支払う形です。
美容師が個人事業主になる際の注意点

「独立すれば自由に働けて、収入が増える」、仲間にそう聞いて独立を考える人も多いと聞きます。しかし、いい面だけを見て決断するのは危険です。
個人事業主になることで、デメリットと言えることも生じます。次のようなことに注意が必要です。
収入が安定しなくなる
個人事業主となれば、勤務時のように毎月安定した給与を得ることができなくなります。
もちろん、相当数の顧客を確保し、経営が軌道に乗れば、サロン勤務より多額の収入を得られる可能性はあります。
ただし、独立してすぐに経営を安定させるのは難しいのが常であり、それまでに資金が底をついてしまえば継続できません。
社会的な信用度が低くなる
収入が安定しないことから、個人事業主は会社経営者やサラリーマンに比べて社会的な信用度が低くなります。
何が困るかと言えば、住宅ローンの契約や、物件の賃貸契約など、信用にもとづく契約・手続きを断られる可能性が高くなる、ということです。
雇い主という後ろ盾の大きさに気づくことになるかもしれません。
集客や営業に力を入れるのは必須
サロン勤務なら、すでに顧客が存在し、施術時に次の予約を入れてもらったりもできます。しかし、個人として独立する場合、自分を指名してくれていた顧客であっても、個人情報の持ち出しは禁止されるケースがほとんどです。
新規顧客獲得のため、SNSアカウントを作って日々発信するなど、自ら行動しなくては集客できません。広告宣伝の方法や、人をひきつける文言も自分で工夫する必要があります。
帳簿付けや領収書の管理も必須
日々の収支は、帳簿に記入します。節税効果の高い青色申告をするには、総勘定元帳と仕訳帳、現金出納帳や売掛・買掛の各帳簿を作成し、5~7年間の保存をすることが義務付けられています。
青色申告の場合は。帳簿も複式簿記でつけなくてはなりません。簿記の知識がないと難しいため、会計ソフトを購入するなどする必要があります。
雑用などもすべて自分の仕事になる
独立を考えるほどですから、勤務先のサロンではアシスタントを卒業し、雑用などをする必要はない人が多いのではないでしょうか。
個人事業主として独立すれば、施術だけでなく電話対応から床の掃き掃除、タオルの洗濯やトイレ掃除まで、自分が行わねばなりません。
あらゆるものにお金がかかる
前の項目に関連して、独立すると、水道光熱費はもちろん、シャンプーから会計時のレシート用ペーパー、トイレットペーパーまで、あらゆる物にお金がかかることに改めて気づかされます。
こうした費用には、お客さんが入らなくても必要となるものも多いです。頭に入れておかないと、予想外の出費に困りかねません。
社会保険にかかる負担が増える
サロン勤務との違いの章でも述べたとおり、個人事業主になると、社会保険を国民健康保険と国民年金保険に切り替える手続きが必要になります。また、保険料は全額自己負担となるため、出費も増えます。
それまで配偶者を扶養に入れていた場合も、配偶者本人が国民健康保険と国民年金保険に加入しなくてはなりません。
従業員を雇う場合は、常時5人以上の雇用で社会保険の適用事業所となり、対象者を健康保険と厚生年金に加入させる義務が生じます。
納税の手続きも自分で行う
所得税などの納税についても、会社による天引きはなくなり、生命保険などに関する年末調整もなくなります。確定申告をして自分で納税額を算出し、期日までに納めねばなりません。
所得が290万円を超えると、個人事業税の課税対象に、1000万円を超えると消費税の課税対象になるなど、勤務時とは異なる税金も必要となります。何が必要かも、自分で調べておく必要があります。
スキルアップや情報把握も自分主体
しかし独立すれば、セミナーや講習会などの開催情報をキャッチするところから始める必要があります。トレンドや新たな機器・商材などに関する情報も、自分から求めに行かなくては入りません。
サロン勤務では、スキルアップのため、セミナーや講習会に参加できる機会を店から与えられます。スタッフ同士の会話から、トレンドなどに関する情報共有もできます。
クレームなどトラブル処理もすべて自分
お客様相手の商売では、クレームなどのトラブルも避けられません。「接客態度が悪かった」「カットやパーマの仕上がりが気に入らない」「薬剤で皮膚がかぶれた」などの苦情は、すべて自分で対応する必要があります。場合によっては、賠償責任を負うことも。
美容系予約サイトやSNSなどに口コミを書かれた場合には、売上に直結するおそれもあります。慎重に対処せねばなりません。
業務委託は「名ばかり事業主」になるおそれあり
業務委託を受けて働く個人事業主については、立場が弱く不利な状況に立たされやすいので注意が必要です。
実際、個人事業主といっても従業員並み、もしくはそれ以上に過酷な労働環境で働かされているケースが少なくないことが問題視されています。
業務委託には、労働法は適用されません。そのため、委託側は労働保険や社会保険の負担、残業手当や経費、福利厚生費などの負担を一切せず、契約した報酬だけで個人事業主を長時間使えるというのが現状です。
サロン勤務の美容師から個人事業主になる手続き

勤務するサロンを辞め、個人事業主になるには、次のような手続きが必要です。
サロンを退職
まずはオーナーに退職の意思を伝えます。就業規則に「1カ月前までに」などの規定があれば守りましょう。
法律上は、退職を申し出て2週間すれば退職(契約解除)できます。しかし、トラブルは避け、なるべく円満に退職するのが賢明です。
社会保険の切り替え
退職したら、14日以内に社会保険の切り替えをしなくてはなりません。市区町村役場に出向き、国民健康保険・国民年金保険への加入手続きを行います。
健康保険・厚生年金からの脱退は、元勤務先が手続きしてくれます。
保健所に開設届を提出
自分のサロンを持つなら、保健所に「美容所開設届」を出すことが必須です。同時に、サロンの構造などがわかる書類、見取り図などが必要です。
サロン施設の検査もあるため、必ず事前に保健所に相談してください。開設届を出した後、検査に合格すれば「確認済証」が交付されます。
確認済証は、サロンに掲示する必要はありません。ただし紛失しても再交付されないため、保管をおすすめします。
確認済証がもらえたら、営業をスタートできます。サロンの開設についての具体的な流れは、こちらの記事で解説しています。
税務署などに開業届を提出
営業を開始したら、1カ月以内に税務署に開業届(個人事業主の開業・廃業等届出書)を提出します。またその時同時に、確定申告を青色申告にするための「青色申告承認申請書」も一緒に出しておくと手間が省けますし、出し忘れも防げます。
青色申告については、「個人事業主がすべき節税の方法」の章で詳しく説明します。
また、個人事業主は、所得が290万円以上だと個人事業税もかかります。そのため、都道府県税事務所にも開業届(名称は地域により異なる)を出す必要があります。
個人事業主ができる節税方法①経費計上

個人事業主になれば、事業で得た所得に税金がかかります。事業にかかった費用を経費に計上することで節税につながります。
税金は、所得から経費を引いた残りの所得にかけられます(課税所得)。経費が多いほど課税所得が減り、そこから算出する税金も少なくなるのです。
ただし、何でも経費にできるわけではありません。
開業の準備費用は「開業費」に
開業の準備段階で必要になったものは、合計が10万円以上となる場合には開業費として「繰延資産」に計上し、何年かかけて少しずつ経費にします。
「開業費」にできるもの

開業費に計上できるものの例を見てみましょう。
- 開業セミナー、スキルアップセミナーなどの受講料
- マーケティング調査に使った費用
- 物件探しやセミナー受講時の交通費・ガソリン代
- 専門家・工事業者との打ち合わせ・相談費用、手土産代
- 参考書籍、文房具、ソフトウェアの購入費
- ショップカードやメニュー表などの作成費用
ただしいずれも、事業に関する支出だとわかる領収書などの保管が必須です。
ちなみに、合計して10万円未満の場合は、開業日の日付でそれぞれの勘定科目による経費計上も可能です。
「開業費」にできないもの
一方、開業費にできないものもあります。例えば次のようなものです。
- 1つが10万円以上となる機器・設備など
- 薬剤などの仕入代金
- 物件取得費(保証金・礼金など)
いわゆる資産の取得費用や、前払いの費用は、開業費には含められません。
ただし、これらは「開業費」としての計上ができないだけで、別の経費にすることができます。例えば10万円以上の機器などは固定資産となり、法定耐用年数に応じて経費にします。
仕入代金は、開業でなく売上に結びつけるべき費用なので、開業費でなく材料費として計上します。
個人事業主が経費にできるもの
経費にできるのは、次のような費用です。ここでは、店舗を持つ場合を例にしています。
表の左側の列は、帳簿につける際の勘定科目です。
| 経費の項目 | 対象となる費用 |
|---|---|
| 地代家賃 | 店舗や事務所の家賃・駐車場代など |
| 材料費 | シャンプーやコンディショナー、ヘアカラー剤など |
| 水道光熱費 | 店舗で使用した水道・電気・ガス代 |
| 通信費 | 店舗で使用した電話、インターネット、郵便など |
| 図書費 | お客様用の雑誌、部屋カタログなど |
| 消耗品費 | ・クシやブラシ、ドライヤーなどの器具、タオルやケープなど ・イスや鏡など什器や設備に該当するもので、取得に要した金額が10万円未満または使用期間が1年未満のもの ・ボールペンや便箋、ティッシュペーパー、洗剤など |
| 広告宣伝費 | ・名刺やショップカードの制作費 ・TVやネットなどメディアを介した宣伝や広告の費用 |
| 荷造り運賃 | 物品の宅配に要した運送料や梱包資材などの費用 |
| 旅費交通費 | ・施術のための出張旅費 ・セミナー・講習会に参加するための移動交通費・宿泊費 |
| 教育訓練費 | 技能の習得などのためのセミナーや講習会への参加費用 |
| 損害保険料 | ・店舗にかける火災保険料や賠償責任保険料 ・仕事で使う車の自動車保険などの保険料 |
| 租税公課 | ・租税=個人事業税や自動車税などの税金 ・公課=国や自治体に払う住民票などの発行手数料や、商工会など公共団体に支払う会費 |
| 人件費 | ・従業員の給与や各種手当 ・社会保険料の事業主負担分 ・通勤費 ・社員旅行などの福利厚生費 |
物件取得費用とは、店舗の賃貸契約にかかる費用です。保証金(敷金)や礼金のほか、前家賃や仲介手数料としてそれぞれ安くても家賃1カ月分(計2カ月分~)が必要です。
また、店舗でもっとも費用がかかるのが、内外装工事です。天井や壁といった構造部分のほか、水回りや空調の工事も欠かせません。
そのため、店舗を持たないフリーランス美容師であれば、物件取得費用や工事費用、機器や什器も揃える必要がないため、費用は大幅に削減できます。
美容師が経費にできないもの

事業に関係ないもの、事業に必要と見なされないものは、費用を払ったとしても経費にはできません。たとえば次のようなものです。
自分への報酬
個人事業主の場合、報酬と言っても自分が稼いだお金を自分が使うことになります。従業員への給与(雇用主からの労働対価)ではないので、経費はできません。
生活費などを事業の口座から落とした場合は、経費とは異なる勘定科目(事業主貸)で処理します。
個人にかかる税金
税金が経費にできるのは、事業に関して課税されるものに限ります。
たとえば所得税や住民税、相続税のように個人にかかる税金は、納付義務によって納めたものです。事業のために要した費用とはいえません。
自動車税や固定資産税は、車や自宅などを事業に使っている場合のみ経費にできます。
制服以外の衣服代・美容代
美容師は人を美しくする職業。「自分の身なりに気を使うのも仕事のうち」と思う人も多いでしょう。しかし、自分の洋服や美容に使ったお金は経費の対象外です。
お客様を美しくするために自分が着飾る必要があるかといえば、ありません。また、事業用と私用の区別もつけられません。
ただし、業務中にしか身に着けないユニフォームやエプロンであれば、経費にすることも可能です。
自宅でサロンを開く場合は?
自宅の一部をサロンにする場合、電気代や水道代、インターネット料金などの支払いは事業とプライベートで分けられません。
その場合は、自宅面積のうちサロンが占める割合などから事業用に該当する費用を計算し、経費とすることができます。これを「家事按分」といいます。
家事按分の方法は限定されておらず、家賃なら敷地面積、電気なら使用時間やコンセントの数の割合から算出するのが一般的です。
個人事業主ができる節税方法②青色申告

個人事業主になると、所得税などの税金は自分で確定申告をして納付する必要があります。
確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2つがあり、青色申告にすることで節税メリットがあります。
青色申告による節税メリット
青色申告は、白色申告より細かく税金額を算出する方法です。そのため国は、青色申告に優遇措置を設け、利用を推奨しています。
青色申告には複数のメリットがありますが、特に大きいのは次の3点です。
- 最大65万円の特別控除
- 赤字の3年間繰り越し
- 配偶者などへの給与を経費に算入可能
青色申告にすれば、特別控除として所得から最大65万円を差し引けます。課税所得が減るため、税金も安くなります。
赤字が繰り越せれば次年度以降の黒字から差し引くことができ、課税所得が減らせます。
家族に手伝ってもらう場合、通常は家族に給与を払っても経費にできません。しかし事前に青色申告を行い、青色事業専従者給与の届出をしておけば、支払った給与を経費に計上できます。
青色申告の注意点
青色申告をする場合、注意すべき点が3つあります。
事前に青色申告承認申請書を提出する
確定申告は、こちらから申請しない限りは白色申告が基本となっています。青色申告にするなら、あらかじめ「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
さらに提出には期限があり、青色申告にしようとする年の3月15日まで、開業時は開業日から2カ月以内にしなくてはなりません。
赤字でも確定申告をしておく必要がある
通常、売上から経費を引いた所得が48万円以下の場合には、確定申告は不要です。
しかし、赤字を繰り越すには、赤字の年にも確定申告をしておく必要があります。
必要ないからと申告しておかなければ、いくら繰り越せるかなどが計算できず、せっかくのメリットが受けられません。
帳簿は複式簿記でつけなくてはならない
複式帳簿とは、1つの取引について「貸方」「借方」の2つに分けて仕訳する簿記の方法です。総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿をその方法で作成します。
白色申告であれば簡易的な簿記でよいですが、青色申告では複式簿記を使わねばなりません。
簿記の知識がないと難しいため、会計ソフトの利用や税理士など専門家のサポートが必須となるでしょう。
美容室の経営を成功させるポイント

スタイリストとしての腕がどんなに良くても、サロン経営も順調にいくとは限りません。
最後に、経営を成功させるために必要なポイントを紹介します。
商圏分析で計画・戦略を練る
店を構えるなら、事前に必ず商圏分析を行いましょう。足を運んでもらうには、立地はかなり重要です。
ターゲット層に合う立地を選び、広告宣伝の方法なども、どれがターゲットに届く最適な方法かを考えます。
商圏分析は、政府の地理情報システム「jSTAT MAP」などのシステム・ツールを使ったり、実際に足を運んで見たりして行います。
事業計画書を作成する
事業計画書は、自身のビジネスとその将来性を第三者にもわかるように文書化するものです。
目標を達成するには計画を立て、それに沿って進めていく必要があります。問題が起こった際は振り返り、改善策を練るにも役立ちます。
銀行など外部からの資金調達を狙うにも、事業計画書の提出が必須です。
SNSをつかって強みを配信

経営の成功は、集客がいかにできるかにかかっています。集客方法には費用がかかる方法もありますが、今はSNSによる集客が当たり前の時代です。
美容サロンについて客側の一番の関心事は、どんなスタイル、カラーにしてくれるのか、どんなヘアアレンジをしてもらえるのか、といったことです。Instagramなどの画像で、自分の強みを伝えましょう。
ただし、どのSNSを使うかもそのSNSの利用者層を考慮して決めないと、効果が期待できません。
リピートしたくなるお店づくり
頻度や期間の違いはあれど、美容院は誰もが継続して通う場所です。ただし、美容院の数はコンビニの5倍近く(※)。一度行って気に入らなければ、2度目の来店はないでしょう。
「またここで(この人に)お願いしよう」と思ってもらうために、施術はもちろん、接客や店内の快適性などに気を配る必要があります。
サロンには、「キレイになれそう/してもらえそう」というワクワク感を持たせる雰囲気づくりも大切です。
※令和4年末時点で、美容所の数は269,889施設(厚労省「令和4年度衛生行政報告例の概況」)。コンビニエンスストアは55,943店舗(商業動態統計速報 2024年3月分速報)
さらなるスキルアップとトレンド把握
独立に成功している美容師の多くは、勉強を欠かしません。常にスキルを磨き、セミナーなどでトレンドの把握や新たな技術の取得をしています。
美容業界自体が流行に敏感な業界であり、お客様は当然プロの美容師は最新の情報やスキルを持っているものと期待しています。
お客さんの希望に沿えたり、自ら提案したスタイルを気に入ってもらえたりすれば、リピーターになってくれる可能性がグンと高まります。
経営や会計、税金などの知識も勉強する
個人事業主となるなら、美容師としてのスキルだけでなく、事業者として必要な経営や会計などの知識も勉強する必要があります。
経営に関しては商工会議所などで学ぶこともできます。会計などについては、簿記3級程度の知識を持って、帳簿の記入や損益計算書などの理解に困らないようにしておきたいものです。
ある程度の収入が得られるようになれば、税理士など専門家に任せるのが一般的です。とはいえ、専門家にもさまざまな人がいます。事業主として、何も知らないまま信頼・丸投げするのには大きなリスクが伴います。
実際に独立開業した美容師の方に聞きました!

事務的な作業や税金の申告など、面倒そうな手続きが増えるとはいえ、実際にサロンから独立し、個人事業主となった美容師の方もたくさんいます。
この章では、実際に個人事業主として美容室を開業された方に状況をうかがった内容を簡単に紹介します。ぜひ参考にしてください。
開業3年目と6年目、収支の状況
AさんとBさんは、それぞれ勤務先の美容室から独立を果たし、現在はご自身のお店を構えています。
- Aさん・・・開業6年目、従業員3名
- Bさん・・・開業3年目、従業員なし
このお2人の年間収支を表で見てみましょう。直近2年間の平均値です。
| Aさん | Bさん | |
|---|---|---|
| 借入 | 450万円 | 800万円 |
| 売上 | 2310万円 | 940万円 |
| 雑収入(協力金等) | 20万円 | 90万円 |
| 仕入 | 510万円 | 95万円 |
| その他雑費 | 1600万円 | 755万円 |
| 利益 | 220万円 | 180万円 |
| 所得税 | 10万円 | 5万円 |
| 消費税 | 80万円 | 0円 |
| 住民税 | 22万円 | 18万円 |
| 健康保険料 | 28万円 | 23万円 |
| 国民年金 | 20万円 | 20万円 |
それぞれのケースで金額が全く異なりますが、この2人の最も大きな違いは、従業員の有無。Aさんには従業員が3名いるのに対し、Bさんは従業員を雇っていません。
スタッフの人数が多ければ、1人で接客・施術するより売り上げも多くなりますし、経費もそのぶん多くかかります。
また、Bさんには消費税の支払いがありません。これはBさんが開業3年目で、開業した年とその翌年には納税義務がないからです。3年目以降は、2期前の売上が1000万円を超えた場合に所得税の課税事業者となり、納税が必要です。
ちなみに、開業2年目であっても前年の1月~6月の間に1000万円を超える売り上げがあった場合には、課税対象となります。
個人事業主3年目、美容師Bさんの状況
Bさんには、開業後の美容室運営についてインタビューにもお答えいただきました。
Q1:開業してよかったことは何ですか?
― 雇われていた時よりも、自分の時間を有効に使えるようになりました!
Q2:開業後に困ったことはありますか?
― あまりないですね。強いて言えば、今後どれくらい続けていけるかわからないってことでしょうか。
Q3:集客はどのようにされていますか?
― 他の美容室ではやっていないことをしていますね。例えば周辺エリアの営業時間帯に合わせて時間帯を変えたりとか。
Q4:これから開業する方にアドバイスをお願いします
― 開業すると、自分の時間ができて自由度が高くなる分、自分に甘くなってしまいがちです。そこをいかに甘くせず、事業に真摯に向き合っていけるかが大切だと思います。
Bさんは、開業後とくに困ったことはないとのこと。事務作業については、従業員がいない分、そこまで負担には感じられていないのかもしれません。
税金関連については、税理士法人に任せられています。
自由に使える時間をどう使うか。そこが開業に成功するか、あるいは失敗するかの分かれ道となりそうです。
美容室の開業・経営ならBricks&UKへ!

店から独立して個人事業主となる方法は簡単ですが、自分の店を持つにも業務委託やシェアサロンで働くにも、収入の確保は簡単ではありません。やるべきこともたくさんあります。
経営や簿記などについても、ゆくゆく人に任せる予定であっても勉強し、書類を見てわかるようにしておきましょう。その上で専門家などのサポートも受けることをおすすめします。
当サイトを運営する「Bricks&UK」は、税理士法人であり、起業や会社設立、事業継承などにも精通した専門家のいるプロ集団です。
融資を勝ち取るための事業計画書の作成などにもお役に立ちます。ぜひお気軽にご相談ください。
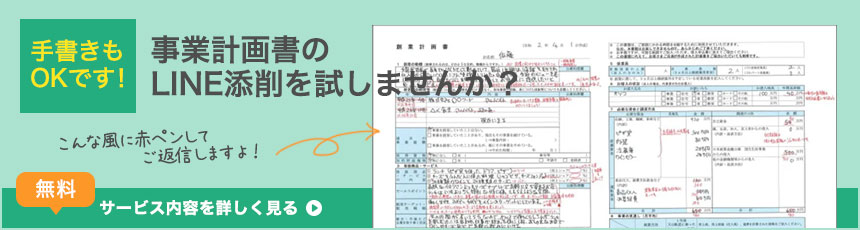
創業時の融資相談もBricks&UKにおまかせください!

当サイトを運営する「税理士法人Bricks&UK」は、顧問契約数2,500社以上、資金繰りをはじめ経営に関するコンサルティングを得意分野とする総合事務所です。
中小企業庁が認定する公的な支援機関「認定支援機関(経営革新等支援機関)」の税理士法人が、日本政策金融公庫の資金調達をサポートします。
資金調達に必要な試算表、収支計画書などを作成してサポートし、借入後の資金繰りもしっかりと見せていただきます。
まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。