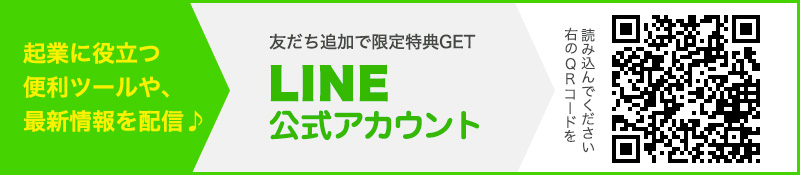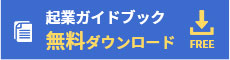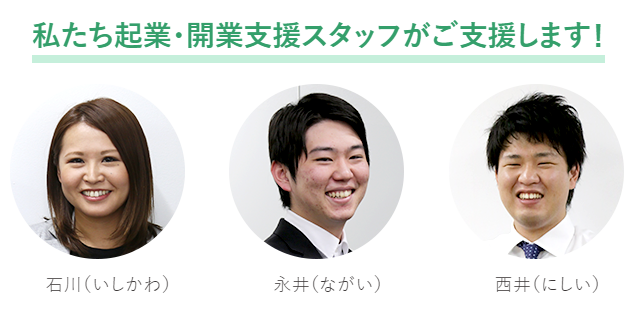雑貨屋を開業したいと思う人は多くても、「何から始めればいいかがわからない」という人や「どんな手続きが必要かがわからない」という人が大半ではないでしょうか。
一般的な雑貨屋の開業に資格は必要ありませんが、古着やアンティークなど中古品を扱う場合や、カフェを併設したりする場合には届出等が必要です。また、雑貨屋に限らず、開業したら税金に関する届出は必須です。
この記事では、雑貨屋の開業に必要な手続きや流れ、資金の相場や調達方法について解説します。
目次
雑貨屋の開業に必要な資格や手続き

まずは、雑貨屋の開業に必要となる資格や手続きについて見ておきましょう。
基本的には資格も許認可も不要

冒頭で触れたように、一般的な雑貨屋を開く、つまり商品となる雑貨を新品の状態で仕入れ、販売する場合、資格や許認可は不要です。
ただし、売り物が新品でなかったり、雑貨以外に許認可が必要なものを売ったりする場合には、許可が必要です。
資格や許認可が必要になるケースもある

雑貨屋で資格や許認可が必要になるのは、次のようなケースです。
- 中古の品を仕入れて売る・受託販売する
- 雑貨屋にカフェを併設する
- 店内で調理した飲食物を売る
もう少し詳しく見ていきましょう。
中古品の販売には「古物商」の許可が必要
雑貨といえば、アンティークやビンテージなど中古の雑貨も人気です。古着や古本などを販売することもあるでしょう。
その場合には、店の所在地を管轄する警察署に「古物商」の許可申請をしなくてはなりません。取得には約1カ月半、申請手数料と住民票などで約2万円がかかります。
盗品の転売などを防ぐために必要とされる手続きであり、無許可で営業し続け利益が大きくなれば、発覚して摘発などされるおそれがあります。
店内での調理には「飲食店営業許可」が必要
雑貨屋にカフェスペースを併設して飲食物を提供したり、コーヒースタンドのような形でカップのコーヒーを提供したりする場合には、飲食店としての営業許可が必要です。
調理をしない、例えば自販機での提供でも、カップ式のコーヒーやジュースの自販機は営業許可の対象です。
また、営業許可を取るのに「食品衛生責任者」の資格が必須。調子免許などがない場合は、講習を受ければ資格が取れます。さらに、建物全体の収容人数が30人以上の場合は「防火管理者」を置く必要もあります。
飲食店営業の許可には、2万円弱(地域により異なる)の手数料がかかります。調理場など施設への立ち入り審査も行われるため、2~3週間はかかると考えておきましょう。
密封で長期・常温保存が可能なら許可不要
雑貨屋でよく見るのが、レジ近くなどで他のお店や個人が作ったクッキーやジャムといった食品が売られている光景です。
すでに包装された状態の、常温・長期保存が可能なものを仕入れて売るなら、許可を取る必要はありません。
製造の許可はその製造元が取っているはずです。もしその食品が自分の手作りなら、「菓子製造業」の許可が必要です。
ただし、飲食物を扱う場合は、どのような種類の食品をどのような方法で提供するかによってルールが異なるほか、地域によっても細かなルールがあります。自己判断でなく、必ず事前に保健所に相談してください。
税金関連の手続きは必須
雑貨屋に資格は必要ないものの、事業で収入を得ることになるため、税金についての手続きは必須です。
個人で開く雑貨屋の場合は、管轄の税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」や、確定申告を青色申告にするための「青色申告承認申請書」を出します。これは所得税に関する手続です。
従業員を雇う場合は、「給与支払い事務所等の開設届出書」や「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出も必要です。
また、都道府県税務署にも事業の開始を届け出る必要があります。これは個人事業税に関する手続きで、届け出の名称や届出の期限は地域により異なります。個人事業税は、事業所得が290万円以上で課税されます。
この他、会社員から個人事業主になった場合には、社会保険(健康保険、厚生年金)の切り替えもしなくてはなりません。
雑貨屋を開業するまでの主な流れ
雑貨屋を開業するためには、まずどんな店にするかを決め、それに合わせた店づくりを進めていきます。1つずつ見ていきましょう。
見やすさのため番号をつけていますが、同時進行したり前後したりする場合もあるので、大まかな流れとして見てください。
1. コンセプトとターゲットを決める

まずは、店のコンセプトを決めます。コンセプトとは、簡単に言えば「どんなお店ですか?」と聞かれたときの答えとなるものです。
コンセプトが固まっていれば、店づくりがしやすくなり、売上も上げやすくなります。
どんな店か
どんな雑貨を売るお店か、何を大切にし、お客さんにどんな価値を提供するかなど、お店の軸となる事柄を決めておきます。
コンセプトが明確であれば、店の内装や店名、仕入れる商品や包装方法など、あらゆることを決めやすくなります。
どんなお客さんに向けた店か
同時に、ターゲットとする客層も決めます。どんなお客さんに来てもらいたいか、来てくれそうかを考えてみてください。
店舗経営の成功には、明確なコンセプトが必須です。業種は異なりますが、こちらの記事も参考にしてください。
2.店舗の運営形態を決める
雑貨屋には、大きく分けて次のような形態があります。
- 実店舗を運営する
- ネットショップを運営する
- 実店舗とネットショップの両方を運営する
当然ながら、実店舗とネットショップを同時に運営すればより多くの集客が期待できます。今やネットショップの開設は必須とも言える状況です。
ただ、店主1人で両方とも運営する場合、ネットショップが片手間となり、管理がおろそかになりがちです。それでは売上もあがりません。
同時に運営するなら、ネットショップ用に人員を確保し、特に在庫管理や発送・問い合わせも実店舗と同じように行うなど工夫が必要です。
ネットショップでの開業については、「雑貨屋をネットで開くことについて」の章で、メリット・デメリットなどを解説しています。
ネットショップの開設前に、ぜひこちらの記事も読んでみてください。
3.経営方法を決める

店舗の経営にも、大きく分けて2つのパターンがあります。
- 自身で個人経営する
- フランチャイズに加盟する
自分で1から店を作り上げるか、すでにあるブランドや経営ノウハウを利用するか。好きなブランドがフランチャイズ展開をしているなら、加盟店となるのも一つの方法です。
ただしどちらにもメリット・デメリットはあるので、それを把握して決めることが重要です。
4.店名を決める
店の名前は、コンセプトに合ったものにします。基本的には自由に決められますが、同業で商標登録がされている名前は避けるようにしてください。
また、奇をてらいすぎたり、流行に乗ったりすると、経営を長く続けていく中で時代とのズレが生じ、変更したくなるかもしれません。
お客さんにとっての読みやすさ・わかりやすさも重視して決めることをおすすめします。
のちに会社設立を考えるなら、商号についても知っておくのがおすすめです。こちらの記事も読んでみてください。
5.事業計画書を作成する
事業計画とは、自分の頭の中だけにある雑貨店のイメージや事業の目的などを明確にするものです。先に決めたコンセプトや経営方法、必要な資金や不足分の調達方法なども記載します。
頭の中を整理でき、不足しているものやすべきことが見えてくるなどの利点があり、経営の成功に欠かせません。
金融機関などへの融資申し込みでも、必ず提出を求められます。
6.店舗の立地を決める
実店舗を開く場合は、お店の立地を決めなくてはなりません。立地は集客を左右する重要なポイントです。決める際は自ら足を運んで競合店舗の有無や人通り、客層や雰囲気などを確認しましょう。
よい物件が見つかっても、家主や不動産会社との契約は必要な資金の調達ができてから交わすことをおすすめします。融資などが必ず受けられるとは限りません。
資金の節約には、まずは自宅の一室や離れなどで自宅開業するのも1つの方法です。
7.資金調達をする
物件にも目途が立てば、資金調達をします。自己資金以外で雑貨屋の資金調達の方法は、主に次の3つが挙げられます。
- 日本政策金融公庫の融資
- 自治体が主体の制度融資
- クラウドファンディング
どんな制度かを簡単に説明します。
日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫は、中小事業主や個人への融資を行う政府100%出資の公的金融機関です。創業者向けには、無担保・無保証人で受けられる融資制度があります。
自治体が主体の制度融資
制度融資は、各自治体が地域経済の発展のため設けている支援制度です。信用保証協会が保証人の代わりとなってくれるため、銀行の融資が受けやすくなります。自治体によっては、金利を一部負担してくれるところも。経営塾への参加が必須な地域もあります。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネット上で不特定多数の人から資金を募る方法です。寄付型・購入型がありまずが、いずれも、いかに応援してもらえるかがカギとなります。廃材利用や発展途上国の支援など、社会問題を解決するような場合に向いています。
8.商品の仕入先を探す
商品の仕入には、次のような方法があります。
- 問屋・商社
- 海外買い付け
- 展示会
- 仕入れサイト
問屋とは、生産者と小売店との間で商品を売る中間業者です。雑貨屋の場合、海外の製品は店主自らの目利きで買い付けてくるケースも少なくありません。
その他、メーカーなどが開く展示会や、インターネットの仕入サイトなどがあります。仕入先は複数確保しておくと安心です。
9.必要な許認可を取得する
中古品やカフェスタンドの併設などには許認可が必要です。オープンに間に合うように申請をしなくてはなりません。
許認可や届出の要・不要がわからない場合は、事前に必ず保健所(食品関連の場合)などに相談・確認してください。
また、飲食店営業許可など施設の審査がある場合は、内装工事にも影響するため、必ず工事に入る前に相談しましょう。
必要な許認可を取得せず営業し、悪質と見なされれば、懲役または罰金が科せられます。
そもそも営業許可は、食中毒等を防止する食品衛生法にもとづく制度です。守らず食中毒などを起こせば、より重大な責任を負うことになります。
10.店舗の内装工事をする
資金調達や許認可の取得などが済んだら、具体的な店づくりに入ります。
内装工事は、なるべく雑貨屋の施工経験が豊富な業者に依頼するとよいでしょう。雑貨屋ならではの内装のポイントを知っている可能性が高いからです。
11.什器・備品などを揃える
内装工事が終われば、雑貨をディスプレイする棚やレジ、包装用のテーブルなどの什器(家具)・備品を揃えます。これらもすべて、最初に決めたコンセプトに合うものを選ぶことが重要です。
什器のレイアウトは、お客さんの動線や目線を確認して決めましょう。万引き防止のため、スタッフからなるべく目が行き届きやすくするのが理想的です。
掃除用具や消耗品などもリストアップして揃えます。
12.広告宣伝を始める

開店してから宣伝するのでは遅いので、早めに動きましょう。
広告宣伝の方法は、地域のフリーペーパーなどを活用する、ショップカードを近隣の店に置いてもらう、SNSのアカウントを開設するなど複数の方法を併用するのがおすすめです。
後の章でもう少し具体的に説明します。
13.商品を仕入れ・陳列する

内装工事を終え、什器・備品なども揃えたら、商品を仕入れて並べます。ただし、入手までに日数がかかるものは、より早めに手配をしておきましょう。
陳列する際も、お客さんの動線と目線を意識して配置します。お店のコンセプトに合わせて、雑多に置くのか、ゆとりをもって置くのかなども工夫してください。
14.店舗をオープンさせる

オープンの日は、時間通りにお店を開け、お客様を笑顔で迎えましょう。来てくれたお客さんには、また来ようと思ってもらえるような接客を心掛けてください。
会計や梱包などのオペレーションは、前日までにシミュレーションをしておくと安心です。
15..開業届など税金関連の届出を出す
会社でなく個人事業主として開業する場合、前述のとおり次の手続きをします。
- 税務署に開業届を出す
- 都道府県税事務所に事業開始届を出す
青色申告にする場合は「青色申告承認申請書」も出しておくと二度手間にならずに済みます。従業員がいる場合は、給与支払い事務所の開設届出書なども提出します。
開業届の提出期限は、開業から1カ月以内です。県税事務所への事業開始届の提出期限は、都道府県により「2カ月以内」「3カ月以内」「翌月の10日まで」などと異なるので、都道府県の公式サイトなどで確認してください。
雑貨屋をネットで開くことについて
ネットショップの市場は、2022年には13兆9997億円と前年より5%以上増加し、コロナ禍ほどではないものの成長を続けています(経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」)。
そのため、ネットショップの開設は雑貨屋としても必須と言えます。しかし、市場規模が大きいと同時に店舗の数も多く、その中で売り上げを確保するのは簡単ではありません。
まずはメリット・デメリットを把握する必要があるでしょう。
ネットで雑貨屋を営むメリット

ネットショップのメリットは、端的にいえば「費用と手間を大幅に削減でき、効率よく物が売れる」ということです。
具体的には次の5つがポイントです。
- 店舗にかかるコストを抑えられる
- 営業時間に縛られず販売できる
- 日本中の人に買ってもらえる
- 開設が簡単にできる
- 副業でもできる
コストが抑えられる
店舗のないネットショップなら、物件の契約や工事、什器・備品などの費用はかかりません。インターネット環境とパソコン、最低限の数の商品や梱包材さえ準備すれば開業できます。
24時間年中無休でオープンできる
また、ネットショップは、年中無休で24時間、常にお店をオープンさせておくことができます。早朝の出勤時間や夜中、昼休みの間にも商品が売れる可能性があります。
日本中の人に買ってもらえる
ネットショップの場合、全国の誰もがお客さん候補となるのも大きなポイントです。通常であれば、公共交通機関で移動が便利な範囲に限られますが、ネットなら日本の端から端までたくさんのお客さん候補が存在します。
開設が簡単にできる
店舗の開設も、ネットなら簡単に出店できるシステムが数多くあります。
商圏分析をして、足を運んで場所を選んで物件を決めて工事をして…という作業がすべて不要です。
副業でもできる
店頭に居続ける必要がないため、1日の大半の時間を店に費やす必要がありません。
そのため、例えばサラリーマンとして昼間は働きながら、入った注文を勤務後の時間に発送するなど、副業としても始められます。
ネットショップ開業のデメリット

ネットショップでネックとなるのは、次のようなことです。
- 商品を実際に手に取ってもらえない
- お客さんの表情が見えない
- 発送作業やメール送信などの手間がかかる
- 専門知識やネットリテラシーが必要
商品をに手に取ってもらえない

雑貨には、手に取ってこそ良さがわかる、試して購入を決めるようなものも多くあります。「わからないから決められない」と購入を見送られるケースも避けられません。
また。例えばプレゼントを選ぶにも、あらかじめ「これ」と決めず、店のラインナップから手に取って選ぶ人も多いもの。そうした選択肢の提供も、すべてシステムや画像と説明文が頼りです。
お客さんの表情や行動が見えない

店であればお客さんの表情や行動でわかることも多いです。しかしネットショップでは相手が見えず、まったくわかりません。
実店舗なら、迷っていそうなお客さんに声をかけられます。「あと一押し」ができれば購入につながり、すすめ方によっては関連商品とのセットで売上を伸ばせる可能性もあります。
こうしたコミュニケーションは、対面ならではです。
発送作業やメール送信などの手間がかかる

店舗では会計時に品物を渡して終わりですが、ネットでは配送用に包装し、発送作業を行う必要があります。注文受付時や商品発送時にメールを送るなどするのも、けっこう手間がかかるものです。
前提として、パソコンでの作業が必須です。ショップの開設は簡単とはいえ、ある程度ネットを使い慣れた人でないとスムーズには行えません。
ネットショップ開業の流れ

開業までの流れも、実店舗とは大きく異なります。大まかな流れを見ておきましょう。
- パソコンやプリンターなどの機器を用意
- インターネット接続契約
- レンタルサーバーの契約/ECプラットフォームへの登録
- ショップページの作成
- 商品の仕入
- 商品の撮影・画像投稿、説明文の記載
- 受注・発送連絡、配送作業
まずはネットショップに欠かせないパソコンとインターネットの環境を整えます。
店舗独自のwebサイトを作り、ショッピングカートなどの設置を1から行うなら、レンタルサーバーの契約が必要です。「BASE」などECのプラットフォームを利用するなら、アカウントを作成します。
ショップページの作成は、まずお店のコンセプトが伝わるデザインにすることがポイントです。一から作るなら、見やすさ、使いやすさなどに重点を置いてください。

商品を仕入れたら、画像を撮影し、ショップページに投稿、説明文も記載します。
商品が売れれば、受注確認のメールを送り、発送手続きをし、発送連絡のメールを送ります。
ネットショップを視野に入れているなら、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
雑貨店が活用すべき5つの集客方法

雑貨屋の経営で資金繰りの次に重要なのが、集客です。特に現在では、インターネットによる集客が売上を大きく左右します。
ショップカードのような、実際に手に取れるものと合わせて、インターネットをうまく活用することが効率よい集客の秘訣です。
主な集客方法を5つ紹介しますが、全部は無理でも、2つ以上は併用することをおすすめします。
店頭の看板

実店舗は、雑貨屋であると認知してもらう必要があります。
看板があれば、そこが雑貨屋であると一目瞭然です。
「○○雑貨店」など、一目で雑貨屋かどうかがわからない場合は、「雑貨屋」「zakka」などの表記や、何が売りかなども書いておくのがおすすめです。
もちろん、看板を出すことは集客といっても最低限と考えておくべきでしょう。
ショップカード

ショップカードはお店の名刺。コンセプトと店主のセンスを伝えるおしゃれなカードを作りましょう。ネットで自作できるサイトもありますが、できればプロにデザインしてもらうのがおすすめです。
作ったら、近隣のお店に置いてもらう、名刺代わりに渡す、商品に同梱する、撮影してSNSに投稿するなど、いろんな場面で使ってください。
デザインさえ決まれば後は必要な枚数を刷るだけなので、労力がいるのは最初だけ。広告宣伝としては比較的安価なのもよいところです。
SNS

SNSは今や必須の集客方法。前述の調査によると、日本のSNS利用者数は、2022年には1億200万人、2027年には1億1300万人に達すると予想されています。
SNSにも種類がありますが、雑貨屋はイメージや具体的な商品説明がカギとなるため、Instagramがおすすめです。
営業時間や商品の入荷状況を伝えたり、人気のランキングなどを動画にしたりするなど、さまざまな工夫ができます。
Instagramのプロアカウントを使えば、店舗の位置情報の表示や広告配信なども行えるようになります。
ホームページ・ブログ開設

ホームページやブログも、少ない費用で効果的に宣伝ができるツールです。
店の公式ホームページを作って、販売サイトとして利用しつつ、ブログを作成・公表することもできます。
例えば雑貨屋にかける思い入れや商品へのこだわり、開業までの大変な道のりなど、バックグラウンドがわかることで、見る人の購買欲を高めることもできます。
スマホ対応の画面にしたりと見せ方などにも工夫が必要なので、サイトの制作はweb制作会社などプロに依頼することをおすすめします。
Googleビジネスプロフィール(旧マイビジネス)

Googleの検索エンジンやGoogleマップなど、さまざまなGoogleサービス上に店の情報を表示できるサービスがGoogleビジネスプロフィールです。
店舗の情報を登録しておけば、Googleで「○○(地名) 雑貨屋」などと検索したときに、Googleマップで店の情報が表示されるようになります。
雑貨屋に来るお客さんは、他の雑貨屋さんと合わせて何店舗かをめぐることも多いため、別のお店に行ったついでで寄ってもらえる可能性も高まります。
雑貨屋に必要な開業資金とその内訳

開業費用は、実店舗とネットショップで大きく異なります。広さ10坪の物件をモデルケースに、両者を比較してみましょう。
| 費用項目 | 実店舗 | ネットショップ |
|---|---|---|
| 物件取得費用 | 150万円 | 0円 |
| 内外装工事費 | 100万円 | 0円 |
| 機器・什器・備品等 | 100万円 | 10万円 |
| 仕入れ費 | 150万円 | 100万円 |
| 運転資金 | 100万円 | 20万円 |
| 合計 | 600万円 | 130万円 |
実店舗の場合、さほど広いスペースがなくとも開業できます。商品の陳列と在庫用のスペースがあればよいため、大量の在庫を抱えるのでなければ、客席が必要な飲食店などに比べて物件取得費も安いです。
内外装の費用も、飲食業のような基準はなく、インテリアもシンプルで事足ります。陳列のための什器は必須ですが、大がかり設備機器も必要ありません。消耗品としては、商品のラッピング代が必須で、商品の価格帯に合うものを選ぶ必要があります。
一方ネットショップでは、物件取得費・内外装工事費が一切かからないので、開業費用は大きく抑えられます。
雑貨屋の開業を成功させるポイント

雑貨というのは、扱う物にもよりますが、生活の必需品でないことも多く、誰もが必要とするわけでない物も多いでしょう。
そのため、飲食店などのように来店=利益とはならず、見るだけで帰る人が他の業種より多い傾向にあります。いかに購入につなげるかがポイントです。
次の7つのポイントはぜひ押さえておきましょう。
他の雑貨店をめぐって参考にする

コンセプトを決める段階で雑貨屋めぐりをし、参考にしましょう。
店内のレイアウトからディスプレイの方法、陳列されている商品の間隔や高さ、POPなどの商品説明やスタッフの声かけ、スタッフ間の連携まですべてが参考になるはずです。
真似したい点を見つけるだけでなく、「これはよくない」「ここはウチの店ではもっとこうしたい」という点を見るのがベストです。
ただし、店内の写真を撮るなどするのはマナー違反なのでやめてください。
まずはフリマイベントなどに出店する

店舗経営や接客の経験がない人は、店舗を作る前にイベントなどで「雑貨屋さん」を経験しておきましょう。
小規模ながらも、どのようにブースをレイアウトし、商品を陳列すればいいか、お客さんにはどう接するとよいかなど、体感で知ることができます。
ハンドメイド雑貨を売る場合は特に、お客さんの反応や売れ具合も見ておく必要があります。価格設定の参考にもなります。
失敗のリスクも小さいので、始めるハードルも低いでしょう。
他の出店者と仲良くなれば、有益な情報交換などもできるようになります。
決めたコンセプトで統一する

最初に決めたお店のコンセプトはあらゆる場面で統一し、ブレたり変えたりしないことも大切です。
コンセプトがブレていると、いくらたくさんの雑貨があっても、その良さを打ち消し合ってしまう可能性大。お客さんも居心地が悪く、滞在時間が短くなります。
コンセプトが変われば、客層も変わる可能性が高まります。そうなれば、それまで来てくれていたお客さんが離れてしまいます。
「お宝さがし」のように、あえて雑多なものを雑多に集めるお店もあります。その場合は、品ぞろえもディスプレイも、とことん雑多にした方が魅力的になるでしょう。
ただ、そういうお店には面白味はあっても、購入に至るかどうかは難しいところです。
入りやすい店づくりをする
歩いている途中でふらりと入ることも多いのが雑貨屋です。
店内が明るい、外からガラス窓で中の様子が見えるなど、「入りやすいお店」であることも重要です。
「何のお店かわからない」「高いかな?」「買わないと出にくい雰囲気だったらどうしよう」など、客が入るのをためらうようなお店では繁盛しません。
在庫の管理を怠らない

基本的なことですが、小売業で失敗するケースの多くが、在庫の管理を怠り、大量の不良在庫を抱えてしまうことによるものです。
雑貨にはトレンドもあり、定番もあります。それぞれに合った在庫管理、発注を行わなくてはなりません。
ネットショップでは、在庫があるにもかかわらず表示をなしのままにするなどして、販売の機会を逃してしまうことも。客が質問できる環境にない分、日々の管理が重要です。
他店にない自店の強みを作る

雑貨屋はどの街にもいくつか存在します。自分の店の強みを作り、それを前面に押し出してお客さんをひきつけましょう。
例えば、自ら海外に仕入れに行っているので、すべての商品について詳しく、ストーリ―が語れる、自分もすべてプライベートで使っているため実用的なアドバイスができる、など。店主の数だけ強みがあるはずです。
特に詳しいジャンルを作ることから、オリジナル商品を作ることまで、お店の成長に合わせて強みも広がるでしょう。
地域や同業者とのつながりを大切にする

地域の人や同業者たちとのコミュニケーションも大切にしましょう。ライバルだからといって過度な敵視は得策ではありません。経営者は孤独だといいますが、仲間がいれば、困ったときに助け合えることもあります。
ささいなことですが、ショップカードを置いてもらったり、「どこかおすすめのお店は」と聞かれたときに名前を出してもらったり。そんなつながりも普段のコミュニケーションから生まれます。
雑貨屋の開業は慎重かつ楽しく始めよう

雑貨屋を開業するなら、まずはコンセプトから決めます。どんなお店にしたいかを考えるのは楽しいですよね。
しかし、成功は簡単ではないため、事業計画を立てるなどしっかりした準備も欠かせません。店舗の立地も十分な下調べのうえ慎重に決める必要があります。
実店舗かネットショップか、自営かフランチャイズかによっても、やるべきことは変わってきます。自分がどうしたいのかをよく考えてから始めてください。
計画をしっかり立てて始めることで、資金が足りなくても融資で調達できたり、やるべきことが明確になり、スムーズな事業運営ができるようになります。
融資での資金調達を狙うならご相談ください!
当サイトを運営する「税理士法人Bricks&UK」は、みなさまの起業・会社設立からサポートいたします。
融資での資金調達を成功させるなら、具体的かつ実現可能な事業計画書の作成は必須。無料添削で書き方のサポートも可能ですので、お気軽にご利用ください。
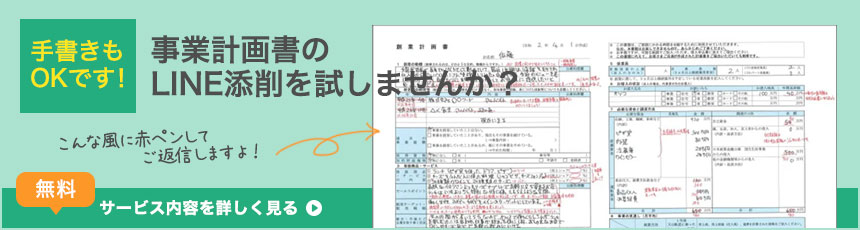
無料相談も承っています。