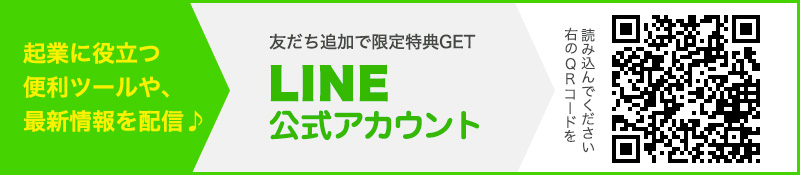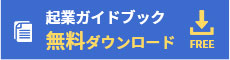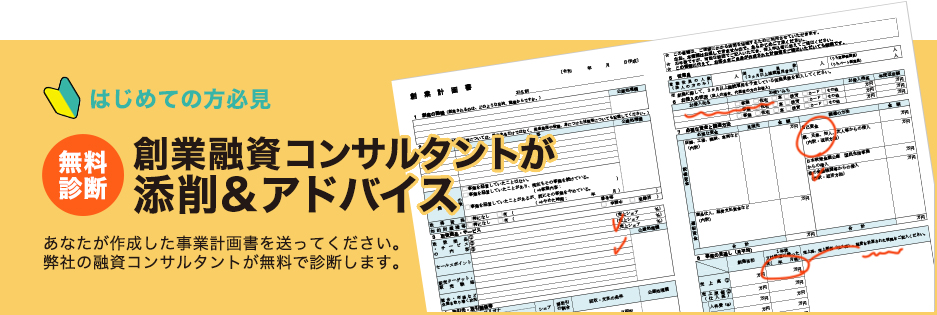飲食店は開業する人の数が多く競争が激しいため、長く生き残っていくにはしっかりとした戦略や工夫が必要です。
実は飲食店経営の失敗には、共通する原因があります。
失敗する人が多いため開業をためらってしまいがちですが、原因を押さえてしっかりと対策を取れば、成功の可能性は十分にあります。
この記事では、飲食店経営に失敗してしまった方の実例を交え、失敗の原因と対策、飲食店経営に欠かせない資金調達のポイントについて解説します。
目次
飲食店の倒産の実態と原因
まずは飲食業界の倒産にまつわる状況を見ておきましょう。
コロナ禍による倒産の状況

コロナ禍の影響を大きく受けた飲食業界では、2022年度全体の倒産件数は3年連続で下回り、592件でした。しかし、2022年の11月以降は5カ月連続で前年を上回っており、コロナ関連の倒産は385件で前年より大幅に増加しました。
また、特にコロナ禍で増えたデリバリーやテイクアウト専門店の倒産が急増しています(以上、出典:東京商工リサーチ「TSRデータインサイト 2023/04/07付」)。
通常営業が可能になった居酒屋やビヤホールの倒産は減っているものの、政府によるコロナ支援が終了したことで厳しい状況は続くと見られています。
飲食店の廃業率

日本政策金融公庫による「新規開業パネル調査」の結果によれば、2016年に開業した企業(全業種)のうち、2020年末まで存続した企業の割合は89.7%。廃業率は8.9%です。
業種別でみると、「飲食店・宿泊業」の廃業率が最も高い結果となっており、14.7%でした。
飲食店経営に失敗する6つの原因

飲食店を経営したいというと、「やめたほうがいい」という人もいます。何も考えずに始めるのは確かにやめるべきですが、計画や失敗への対策をすれば諦める必要はありません。
飲食店経営に失敗する原因は複数が絡むことも多いですが、次のような点が共通しています。
- 店のコンセプトがはっきりしない
- 商圏や市場、競合店の調査をしていない
- 客のニーズより自分のこだわりを優先する
- 集客を後回しにする
- 人材の適切な管理ができていない
- 自己資金の用意が十分でない
それぞれ見ていきましょう。
失敗原因 1. 店のコンセプトがあいまいだった
コンセプトとは、店の統一的なテーマのようなもの。店づくりの重要な土台です。
店はコンセプトにより個性が作られます。そしてそこに魅力を感じたお客さんが集まります。コンセプトがない店では客も定着せず、別のもっとわかりやすい魅力がある店に流れてしまいます。
失敗原因2. 商圏や市場、競合店の調査をしていない
商圏分析とは、国勢調査など国の統計や業界のデータなどを活用し、出店するエリアの市場規模や特性を把握することです。
商圏分析を詳細に行うことで、ニーズや競合店舗の状況が見えてきます。成功に必要なのは社会や客のニーズに合わせて店舗やメニュー、サービスを作っていく「マーケットイン」の発想です。
たとえば前項のコンセプトがはっきりしていても、ニーズとズレていれば、思うような集客は見込めません。
失敗原因3. 客のニーズより自分のこだわりを優先する
お客さんのニーズより自分のこだわりや理想を優先させてしまうことも、失敗する原因になります。
自分の理想がお客さんの理想と同じとは限りません。その違いが大きいほど客足は遠のきます。お客さんのニーズを重視しないと、その違いに気づくこともできません。
また、こだわりの実現のため、多額の初期費用をかけてしまう人も多いです。飲食店はただでさえ家賃などの固定費や仕入れに利益を圧迫されやすい業種。自分の理想を求めすぎて集客ができなければ、経営は行き詰まります。
失敗原因4. 集客活動をおろそかにする
店を知られていなければお客さんは来ないので、開店前から積極的にアピールしていく必要があります。
ですが、飲食店の開業には物件の取得や厨房機器など目に見える必須な物が多く、費用がかかります。そのため、集客に資金を使いたがらない人も。
しかし、経営が安定するためには、まず来てもらうのはもちろん、二度三度と来てもらい、常に新たなお客さんをも取り込まなくてはなりません。そのための集客をおろそかにすれば、売り上げは上がりません。
失敗原因5. 人材の適切な管理ができていない
飲食店では、人材の管理も売上に影響します。多いのは人手不足なのに人件費を節約しようと少人数で無理をしてしまうケース。
優秀な調理人がいることで好調な売り上げを確保できていた場合、その人物がいなくなれば味が落ちて不評となり、閉店に追い込まれるケースも。
逆に、客数のわりにスタッフが多すぎて、人件費が経営を圧迫するケースもあります。
失敗原因6. 自己資金の用意が十分でない
自己資金が十分に貯まっていない状態で事業を始めてしまうことも、失敗につながります。資金ゼロでは開業も困難ですし、成功の可能性は低いです。
開業資金は融資で借りるのが一般的ですが、それはあくまで「自己資金で足りない分」です。借りるにも必要総額の30%以上の自己資金があることなどが条件となっています。
また、開店してもすぐに黒字となるケースは稀で、数カ月は赤字でも持ちこたえる必要があります。その間に資金が尽きれば、成功するものも成功できません。
融資で借りられるのは事業用の資金だけなので、生活費の確保も必須です。
【実例から学ぶ】飲食店経営に失敗する原因
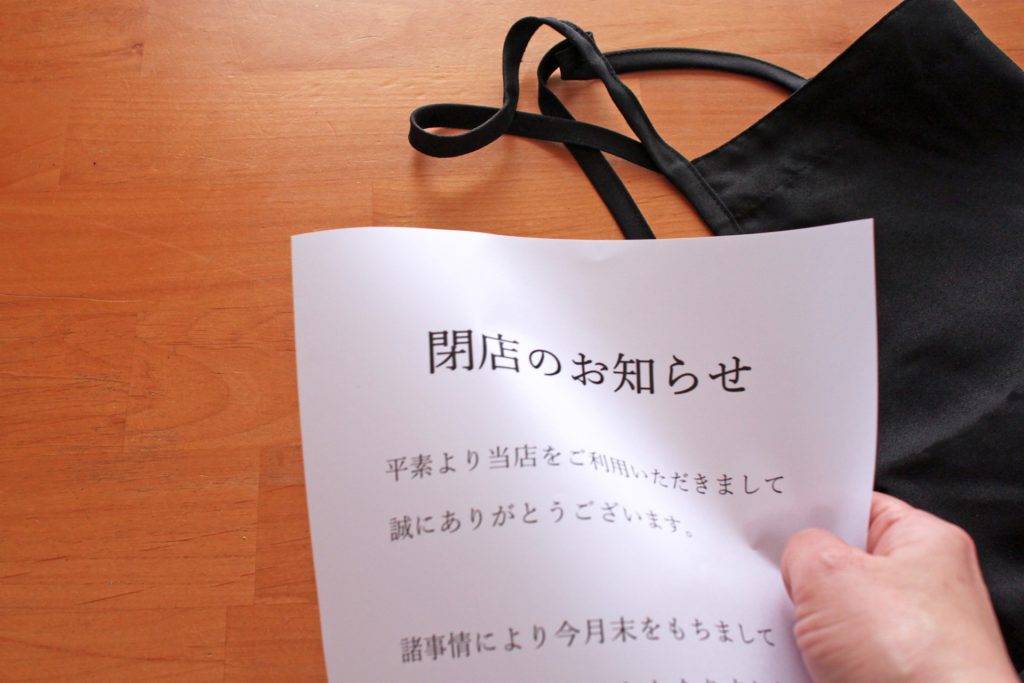
飲食店経営者のAさんは、飲食業界で長年勤めた後に、当時流行していたタピオカミルクティーのお店をオープンさせました。しかし、数年で廃業を余儀なくされてしまいます。
Aさんが店舗経営撤退に追い込まれた経緯

Aさんがどのようにして経営の撤退を余儀なくされたのか、その経緯を見ていきましょう。
経営ノウハウのないまま流行に…
タピオカミルクティーのお店だけでなく、Aさんは当時同じように流行っていたかき氷店やチーズボールの店などの経営にも乗り出しました。
その後もコンセプトカフェの流行に乗って、接客を伴う飲食店(いわゆるガールズバー)の運営を行ったり、他にも飲食関連のさまざまな業態のお店を買収したりして精力的に経営拡大を続けていきます。
膨らむ設備投資
Aさんは、流行に乗ろうと店舗の買収を繰り返します。そのため設備投資はどんどん膨らんでいきました。
本来ならそれぞれの業態に合わせた経営で売上を上げ、投じた資金を回収すべきです。しかし、Aさんにはそういった経営知識がありませんでした。
感染症の拡大が追い打ちに
何とかしなければ、と思ったその矢先、新型コロナウイルス感染症の流行が拡大します。
経営の立て直しを図るべく拠点を移しましたが、その頃から金融機関との連携も取れにくくなってしまいます。事業拡大についても、金融機関には知らせていないままでした。
法律違反を犯していると知らず
Aさんが手がけた事業の1つ、ガールズバ―の営業は、風営法でいう「接待飲食等営業」に当たります。Aさんはこれも知らなかったことで、状況がますます悪化します。
公安委員会に許可申請を行う必要があると知らず、無許可営業、事実上の風営法違反となっていたのです。
労務管理にも問題が…
さらに、ガールズバーの営業を昼の部と夜の部に分け始めたことで、従業員の労務的な管理が行き届かなくなりました。
そしてついに、社会保険料の未納も発生させてしまいます。
金融機関からの信頼も失墜
金融機関から開業時に受けた融資は、申請した事業に対するものであり、別の事業に使うのはNGです。
しかし、金融機関との連携が疎遠になっている間に、別業態の事業経営にもその資金を使っていたAさん。これが発覚し、審査を一から受け直すことに。
そしてその後、社会保険料未払いという公金の債権が明らかになりました。この時点で、銀行はAさんからの債権の回収見込みはなしと判断。融資を打ち切られてしまったのです。
ついに撤退
資金繰りが難しくなった上、非接触などコロナ禍で必要とされる「ニューノーマル」にも対応できないまま、売り上げはどんどん落ち込み、経営は悪化の一途をたどります。
新たな資金調達の見込みもなく、Aさんはついに、店舗経営から撤退せざるを得なくなりました。
Aさんの失敗の原因とは

この経営失敗には、5つの原因が挙げられます。
- 業態に合った経営ノウハウを学ばず別業態に手を広げた
- 綿密な計画を立てることなく流行りものに手を出した
- 従業員の労務管理・手続きを怠った
- 上記のような理由により金融機関の信用を失った
- コロナ禍を甘く見てしまった
飲食店の開業には、保健所の営業許可などは必要なものの、知識の有無を図る資格は不要です。開業を考える人が多いのも、それが理由の1つと考えられます。
しかし、やはり飲食や経営、法律などの知識は経営の成功に欠かせません。
さらに、当初から税理士や経営に関する専門家がついていたものの、相談することなく事後報告で済ませたりアドバイスに従わなかったりしたことから、立て直しへの選択肢がどんどん減っていった、という背景もありました。
飲食業に限らず、事業の成功には、綿密な事業計画を立てることが不可欠です。流行っているから、なんとなく、と流されるような経営では、一時的にうまくいくことはあっても継続できません。
事業計画・創業計画書については最後の章「飲食店の成功に欠かせない資金調達のポイント」で解説します。
飲食店経営に失敗しないために必要な対策

上で紹介した例を踏まえると、まずは事業への知識や理解を深めること、綿密な計画を立てることは不可欠です。
その上で、次の点も押さえておきましょう。
- 店のコンセプトを明確にする
- 店の立地は厳選する
- 客のニーズや人の意見を重視する
- 集客に力を入れる
- スタッフを大切にする
- キャッシュフローの管理を徹底する
順に解説します。
店のコンセプトを明確にする
成功している飲食店はコンセプトが明確です。「誰にどんな料理・サービスを提供するか」をしっかりと考えて決めましょう。
特定のターゲットに深く刺さるものほど確かな集客が見込めます。
まず、ターゲット層を決めたら、市場調査でターゲットのニーズを把握し、それに合わせて業態や提供する料理のジャンルなどを決めます。さらに、店の内装やメニューを決めます。
このように、大まかなことから具体的なことへと順に決めていきましょう。そうすると、資金計画も立てやすくなります。
店の立地は厳選する
やはり飲食店は、立地によって売上が大きく左右されるものです。よほどの魅力がない限り、またそれが広く知られていない限り、人は通うのに便利なお店を選ぶからです。
安い物件や居抜き物件には、店が続かない場所的な原因がある可能性が高いです。自分の店なら大丈夫だろうと過信せず、慎重に決めなくてはなりません。
あわせて読みたい
客のニーズや人の意見を重視する
どの業種でも、お客さんがいてこそ商売は成り立ちます。数の多い飲食店こそ、ニーズを重視してお客さんを1人でも多く取り込まないと、競合店に勝てません。
市場調査などでニーズを把握したら、ニーズを満たすメニューやサービスを用意しましょう。ただしこの分析も、独りよがりでは間違う可能性があります。
人の意見にも素直に耳を傾ける姿勢と、柔軟かつ迅速な行動が必要です。
あわせて読みたい
集客に力を入れる

安定して利益を上げるためには、集客への注力は必須です。集客は、飲食店の経営成功の重要なカギの1つです。
ただし広告宣伝費のかけすぎも経営の負担となるので、方法は厳選すること、効果測定をして要・不要を判断することが重要です。
集客方法には次のようなものがあります。
- チラシの配布
- フリーペーパーへの広告掲載
- 飲食店予約サイトへの登録
- ホームページ・ブログの開設
- SNSの投稿
- メールマガジンの配信
- デリバリーサイトへの登録
デリバリ―可能なメニューがある場合、「ウーバーイーツ」のようなサイトを活用すれば配達する人材や時間の節約ができます。
ただしこれも初期費用や手数料がかかるので、注文頻度や収支を考えて経過を見る必要があります。
あわせて読みたい
人材の流出を防ぐ

飲食業は慢性的に人手不足の状態といわれ、「いかに良い人材を確保するか」はどのお店でも課題となっています。
しかしその前に、今いる優秀なスタッフを辞めさせない工夫が必要です。
そのためには、日々のコミュニケーションを円滑にし、店が目指すところ(コンセプトなど)を共有し、協力体制を作ることが大切です。もちろん、適正な賃金を払い、不満が生じないようにしなくてはなりません。
あわせて読みたい
キャッシュフローの管理を徹底する

キャッシュフローをきちんと管理していないと、利益は出ているのに手元の資金が足りなくなり、ローンの返済などが滞って「黒字倒産」するリスクがあります。飲食店の倒産ではこの黒字倒産も少なくありません。
1日あるいは月単位でお金がいくら入りいくら出ていくのか、資金繰り表を使って入出金をしっかりと把握・管理することが重要です。
資金繰り表とは、現在の手元資金から将来の出入金を差し引きして、将来の手元資金を計算する表のことです。
あわせて読みたい
飲食店の開業時に欠かせない資金調達のポイント

店舗経営には多額の費用がかかるため、自己資金と融資などの資金調達方法をいくつか使って必要な額を集めるのが一般的です。
しかし、これから創業するという事業実績のない時期にお金を借りることは難しいという実状もあります。
ここでは、飲食店の開業資金を調達するのに押さえるべきポイントを解説します。
日本政策金融公庫の創業融資を利用する

開業資金の融資を申し込むなら、第一候補となるのが日本政策金融公庫です。
日本政策金融公庫は、一般的な銀行と異なり、政府が100%出資する金融機関。預金などは受け付けておらず、個人や中小企業への融資をメインに行っています。
国の「起業率を高めたい」狙いもあり、民間の銀行より有利な条件で、積極的に融資をしてくれます。
新規開業する人には、無担保・無保証人で融資が受けられる制度があるほか、女性、あるいは若者・シニア向けに特別利率が適用される制度などもあります。
あわせて読みたい
融資が通りやすい創業計画書を作成する

どの金融機関から融資を受けるにも、創業計画書の作成は必須です。しかも、空欄を埋めただけのものやいい加減な内容では審査に通りません。
というのも、実績のない創業時には、事業計画書がどこまで現実的で具体的に作り込んであるか、というのが経営の成功可否を判断する重要なポイントだからです。
融資ですから、貸した側はその後に返してもらわねばなりません。そのため、返す能力がなさそうと判断されれば、融資は受けられません。
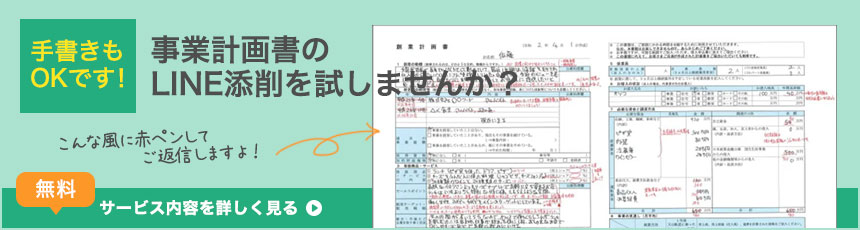
融資審査に精通した専門家を味方にする

経営経験のない人がいきなり融資に通る事業計画書を作るのは難しいものです。しかし、融資審査に精通し、何人もの前例を見てきた専門家なら、創業計画書で押さえるべきポイントも把握しています。
おすすめしたいのは、税理士や税理士法人によるサポートを受けることです。費用はかかりますが、開業後の会計や税務など、継続して頼るべきこともたくさんあります。
多くの企業が税理士などと顧問契約していることでもわかるように、本業に専念して経営成功に導くには、分野違いのことは専門家に任せるのが賢明な方法です。
あわせて読みたい
飲食店の経営を成功させるために

毎年多くの飲食店が生まれますが、多くの飲食店が資金繰りに失敗するなどして閉店します。経営を成功させるには、前例から学ぶことが大切です。
失敗した飲食店には、いくつかの共通する原因が存在しています。飲食店の開業に後悔しないためにも、開業前にしっかり把握をし、対策をしていきましょう。
開業資金を融資でまかなおうとしているなら、融資を申し込む先の選択や創業計画書の作り込みも必須です。とはいえ簡単なことではないので、専門家の活用をおすすめします。
当サイトを運営するBricks&UKは、税理士法人を母体とする事業経営の各種専門家を擁する総合事務所です。
事業計画書の無料添削や、創業融資の無料診断なども行っているので、ぜひお気軽にご相談ください。