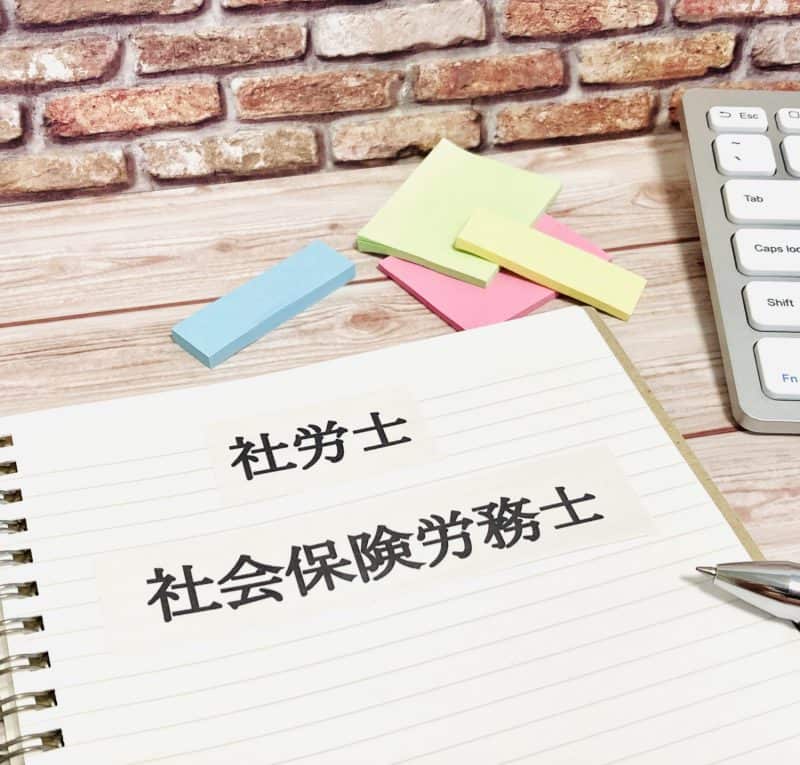起業したいと思っても、何から始めればいいのか、資金はどうすればいいか、など疑問点は多いものです。
誰かに聞きたくても、誰に聞けばいいかわからない…そんな人も少なくありません。親や知人、先輩起業家でもいいですが、より最適な答えを知るには専門の窓口に相談するのがおすすめです。
この記事では、起業前に信頼して相談できる窓口を紹介します。相談前にしておくべきこと、相談時の注意点なども解説するので参考にしてください。
目次
起業について相談できる窓口
では、実際に誰に相談すればいいのでしょう。まずは、無料で幅広い内容について相談できる窓口を利用するのがおすすめです。
この章では、起業についての無料相談が可能な公共性の高い窓口を紹介していきます。
- 商工会議所・商工会
- 自治体の中小企業支援センター
- よろず支援拠点
- 日本政策金融公庫
- 中小機構
- ワンストップ相談窓口Plus One(プラスワン)
- 起業ライダーマモル(チャットボット)
それぞれ説明します。各自治体に分けて設けられている窓口については、この後の「5大都市圏の起業相談窓口一覧」の章で紹介します。
商工会議所・商工会

起業に関する全般、特に創業計画書の策定やビジネスモデルの構築、ビジネスパートナー探しなどの相談に向いているのが、商工会議所や商工会です。
商工会議所も商工会も、地域経済の発展や中小規模の事業主への支援を行う団体です。商工会議所は主に「市」単位、商工会は「町村」単位で存在しています。
「商店街の空き店舗を借りて事業を始めたい」というようなケースでも、話が早く進むでしょう。
事業を始めようとする地域の、商工会議所あるいは商工会が相談窓口です。
中小企業支援センター

ベンチャーやスタートアップの起業、ビジネスプランの策定や資金調達などに関して相談できるのが、各自治体にある中小企業支援センターです。
全国47都道府県のほか、政令指定都市にあり、地域の中小企業・小規模事業者のサポートをしています。
名称は各地で異なりますが、いずれも大枠は公益財団法人であり、「○○○(地名)産業振興センター」「○○〇(地名)産業振興財団」などとなっています。
都道府県等中小企業支援センター(令和5年9月現在)|中小企業庁
よろず支援拠点

中小企業や小規模事業者の起業や経営に関するあらゆる相談に乗ってもらえるのが、全国にある「よろず支援拠点」です。国が運営する相談所なので、安心して利用できます。
さまざまな専門家が集まっているので、あちこちに相談に行かずともここだけで解決できる可能性もあります。
日本政策金融公庫

創業計画や資金計画の策定、融資による資金調達の相談に向いているのが、日本政策金融公庫です。
国が100%を出資する政府系の金融機関なので信頼度が高く、創業時に融資を受ける人が多いことで知られています。全国各地に支店があります。
民間の銀行でも相談には乗ってもらえます。しかし、「自行の利益になるかどうか」が影響し、偏った回答になるおそれもあります。
中小機構

中小機構(独 中小企業基盤整備機構)でも、起業や経営に関するあらゆる相談が可能です。
例えば、これからニーズが高まるビジネスを知りたい、事業に使える公式な補助金制度を知りたい、自己破産の過去があっても会社設立が可能か知りたい、など。
スタートアップや海外に向けたビジネスに関する相談にも向いています。
ここで言う「スタートアップ」は、創業時の企業全般ではなく、独創的な技術やアイデアで急成長が見込める企業を指します。
AIチャットボットや専門家にチャットで相談できるサービスもあります。
ワンストップ相談窓口Plus One(プラスワン)

スタートアップの場合、研究開発などに多額の費用がかかります。そんな資金面やビジネスマッチング、知財の実用化などについて相談したい、国の援助を受けたいという場合には、「Plus One(プラスワン)」の利用がおすすめです。
「Plus One(プラスワン)」は、スタートアップを支援する政府系の16機関による、ワンストップの相談窓口です。
起業ライダーマモル(チャットボット)
「起業ライダーマモル」は、LINEをつかったAIチャットボットです。起業に関する相談に、AIが最適なアドバイスを提案します。相談内容によっては活用するとよいでしょう。
運営する中小機構によれば、令和5年9月現在で約10万2000人が登録していると言います。
起業や経営に関する相談だけでなく、起業のアイデアをスマホにまとめて事業計画書の作成に役立てる「マイノート」という機能があり、そのマイノートを専門家に添削してもらうこともできます。
起業の際に相談できる専門家

相談したい分野が限られている場合は、次のような各分野の専門家に相談した方が話が早いでしょう。
| 名称 | 専門分野 |
|---|---|
| 弁護士 | 法律に関する全般 |
| 税理士 | 税金に関する全般、企業経営、補助金申請 |
| 司法書士 | 会社設立などの登記・供託、裁判所等への書類作成 |
| 行政書士 | 行政機関に提出する書類の作成 |
| 社会保険労務士 | 雇用・労働保険、社会保険、助成金申請 |
| 中小企業診断 | 中小企業の経営指南、課題解決 |
ただし、専門家個人や民間法人に相談する場合は、相談が無料かどうかを確認してから利用するのがおすすめです。
弁護士

起業には、さまざまな法律も関わってきます。特に注意すべきなのは、立ち上げる事業に法的な問題がないか、ということです。
新たなビジネスであれば特に、どんな法律が関わってくるのかを知り、遵守する必要があります。弁護士は法律全般のプロなので、事前に相談すると安心です。
日本弁護士連合会(日弁連)では、中小企業向けの相談ダイヤルを設置しています。
税理士

法人税や確定申告、インボイス制度など税金に関することは、税理士の専門分野です。
また、税理士は事業計画や経営支援も行っているほか、補助金の申請などにも精通しています。そのため、税理士と顧問契約を結び、経営に関する相談もしている事業主が多いです。
各地方の税理士会では、税金に関する無料相談を行っています。「○○(地名) 税理士会」でネット検索してみてください。
司法書士

司法書士は、会社設立に必須の「登記」の専門家です。そのほか、株式会社の設立に欠かせない、「定款(会社の基本事項を定めたもの)」を公証役場に認証してもらう手続きの代行も可能。
法務局や裁判所・検察庁などに提出する書類の作成もしてくれます。
各地の司法書士会で、無料の法律相談を行っています。「○○(地名) 司法書士会」でネット検索してみてください。
行政書士

起業に際しては、さまざまな場面で法的な書類を作る必要があります。国や自治体の役所といった行政機関に提出する書類の作成については、行政書士が専門家となっています。
営業許可の取得が必要な業種などは、書類の書き方が許認可の可否を左右することも少なくありません。自分で作成することに限界を感じたら相談してみましょう。
行政書士会でも、各地で無料相談を受け付けています。「○○(地名) 行政書士会」で検索してみてください。
社会保険労務士

起業と同時に会社を設立したり、従業員を雇ったりする場合に頼れるのが社会保険労務士です。
雇用保険・労働保険といった保険の手続きや、就業規則の作成、雇用関連の助成金申請などを専門としています。労基法の遵守も必須ですので、事前に相談しておくとよいでしょう。
各地の社会保険労務士会で、無料相談を行っています。「○○(地名)社労士会」で検索してみてください。
中小企業診断士

中小企業診断士は、文字通り中小企業が持つ課題の解決をサポートする専門家です。ビジネスモデルから資金繰り、集客、ITの活用など、経営に関するあらゆることを相談できます。
中小企業診断士は、上で紹介したよろず支援拠点や、商工会議所の相談窓口でも活躍しています。
中小企業診断士協会も各地にありますが、無料相談は行っているところと行っていないところがあります。「○○(地名)中小企業診断士協会」で検索してみてください。
5大都市圏の起業相談窓口一覧
この章では、いわゆる5大都市圏に絞って相談窓口を紹介します。
青色の文字部分から、各窓口の公式サイトに移行できます。相談方法は電話・オンライン・対面が選べるものなどそれぞれことなります。事前予約が必要な窓口もあるので確認してください。
札幌の起業に関する相談窓口

| 相談窓口 | 備考 |
|---|---|
| 札幌中小企業支援センター (さっぽろ産業振興財団) | 融資案内、女性起業家向けなど複数の窓口あり |
| さっぽろ創業支援プラザ (札幌商工会議所) | 「創業全般」あるいは「法人設立」での相談 |
| 北海道信用保証協会 | 創業融資に関する保証審査などの相談 |
| 創業サポート相談室 (地域経済局中小企業課) | 創業時の融資制度や助成金制度などの相談 |
| 経営アドバイス(札幌) 中小機構北海道本部 | 事業計画やビジネスコンセプトの作成、資金調達など |
| 北海道よろず支援拠点 (北海道中小企業総合支援センター) | 経営についてのあらゆる相談が可能 |
| STARTUP HOKKAIDO (スタートアップ北海道) | スタートアップ(革新的なアイデアでの起業)を考えている人向け |
東京の起業に関する相談窓口

| 相談窓口 | 備考 |
|---|---|
| 創業アシストプラザ (東京信用保証協会) | 創業ノウハウの提供、創業計画書の作成支援、資金面での相談 |
| TOKYO創業ステーション | 事業計画書の作成や融資についての相談のほか、先輩起業家への相談も可能 |
| 東京開業ワンストップセンター | 法人設立に関する手続きをワンストップ(1ヵ所)で行うことも可能。英語の対応も常時可能。 |
| 東京都よろず支援拠点 (東京都信用保証協会) | 創業前の準備から創業後の計画作成、売上拡大、HPの作り方などあらゆる相談が可能 |
| 東京ビジネスサポートプラザ (日本政策金融公庫) | 土曜や夜間の相談も可能 |
| 東京都企業立地相談センター | 不動産専門のアドバイザーが、事業所を設ける場所についての相談にのってくれます。 |
名古屋の起業に関する相談窓口

| 相談窓口 | 備考 |
|---|---|
| 名古屋市新事業支援センター (名古屋産業振興公社) | あらゆる角度から経営についての相談が可能 |
| 名古屋市信用保証協会 | 計画が具体化していない段階での相談も可能。 名古屋市新事業支援センターとも連携。 |
| 創業プラザあいち (あいち産業振興機構) | 相談スペースのほか、事業計画書の作成などができるスペースなどあり。 |
| 愛知県よろず支援拠点 (あいち産業振興機構) | 経営、マーケティング、IT、税務などあらゆる分野の専門家に相談可能。 |
| 名古屋市小規模事業金融公社 | 経営や融資に関する相談が可能。事業資金の融資も実施。 |
| 名古屋ビジネスサポートプラザ (日本政策金融公庫) | 土曜や夜間の相談も可能。」 |
大阪の起業に関する相談窓口

| 相談窓口 | 概要 |
|---|---|
| 大阪産業創造館 経営相談室 | 起業アイデアの整理からDX推進、海外展開まで幅広く相談可能。 |
| AIDOR(アイドル) エクスぺリメンテーション (ソフト産業プラザTEQS/大阪産業局 ) | IoTやロボット、AIなどを活用した製品・サービスの実証実験をサポート。 事業化に向けた相談が可能。 |
| STARTUP CAFE OSAKA (関西大学内) | 起業前の人のみを対象とした無料相談。 ビジネスモデルや事業計画書の作成について相談可能。 |
| 大阪府よろず支援拠点 | どこに相談してよいかわからない、という段階から対応可能。 |
| 大阪DX推進プロジェクト「OBDX」 (大阪産業局) | IT・デジタル分野についての相談、DX活用方法などの相談に特化。 |
| 大阪ビジネスサポートプラザ(日本政策金融公庫) | 土曜や夜間の相談も可能。 |
福岡の起業に関する相談窓口

| 相談窓口 | 概要 |
|---|---|
| 福岡市中小企業サポートセンター (福岡商工会議所) | 創業から経営全般、ITや法律相談まで可能。 |
| 福岡県よろず支援拠点 (福岡県中小企業振興センター) | 何をやりたいかわからない人のための創業相談もあり。 |
| 福岡商工会議所 創業・起業支援 | 何から始めればいいのかわからない場合にも相談可能。 |
| 中小機構九州本部 経営アドバイス | ビジネスプランや事業計画の作成から、税務会計、特許権や商標権まで対応可能。 |
| INPIT 福岡県知財総合支援窓口 | 知的財産に関する疑問などに応える窓口。 |
なお、いずれも初回の相談が無料なものばかりですが、詳しい内容について専門家の紹介を受けるなどした場合には有料となる場合があります。料金については都度相談先に確認してください。
相談できること・しておきたいこと

起業前に相談したいことはたくさんあります。自分でどこまで考えたり行動したりしたかによっても異なるでしょう。
「専門家の人にこんな初歩的なことを聞いてもいいのか」と遠慮することなく聞いてみてください。
相談できること
ここで紹介した相談窓口では、まず話を聞き、その相談に的確なアドバイスが可能な専門家を紹介されるシステムになっていることも。そのため、「○○について知りたいが誰に相談すればいいか」とたずねてもOKです。
そのほか、例えば次のようなことが相談できます。
- 創業に必要な手続きや届出について
- 起業するビジネスに必要な自己資金額
- 創業資金の調達方法、融資について
- 創業計画書(事業計画書)の作成方法
- 販路の開拓方法
このほか、起業しようとするビジネスが成功できるかどうか、といった相談も可能。何かしら障害となることや盲点などが見つかるかもしれません。
相談しておきたいこと
自分が知りたいこと以外でも、知っておけばよかった、こうしておけばもっと税金が節約できたのに、と後悔する可能性があります。次のようなことも相談しておくとよいでしょう。
- 起業の形態
- 資金調達の方法
- 創業計画書の作り方
- 必要な許認可や手続き、書類
それぞれについて説明します。
起業の形態
起業にも、個人事業主として起業する場合と、会社を立ち上げる場合があります。また、飲食業を始めるにも、店舗を設けるかテイクアウト専門のキッチンカーにするかといった複数の方法があります。
また、会社を立ち上げるにしても、「株式会社」か「合同会社」などの選択肢もあります。経営の難易度や節税の面で、どういう形態がいいのかも聞いておきたいところです。
資金調達の方法
資金をどこから調達すればいいかも、多くの起業家が悩むところです。
金融機関に融資を申し込むだけでなく、各自治体が設けている創業支援など、相談すれば耳寄りな情報が手に入るかもしれません。
スタートアップ(革新的な技術やアイデアで起業する)であれば、国からの支援が受けられる可能性もあります。
創業計画書の作り方
起業には、創業計画を立てることが必須です。創業計画は、「創業計画書」として書面にまとめるのが一般的。経営に役立てるのはもちろん、融資の審査でも重要視されます。
いわゆるテンプレートで空欄を埋めるだけでは融資が下りない可能性も高いので、計画の立て方や書き方のポイントを教えてもらいましょう。
必要な許認可や手続き、書類
起業するには、個人なら開業届、会社なら設立登記を行う必要があります。また、事業によっては許認可や届出等が必要なケースも少なくありません。
自分が行う事業にはどんな手続きが必要か、用意すべき書類やその書き方など、ケースによって違います。ミスやもれのないよう、確認しておくと安心です。
起業の相談前にしておくべき準備

起業を誰かに相談する前に、しておくべきことがあります。5つの準備行動とその理由を見ておきましょう。
- 起業の目的を明確にする
- 本やネットで下調べする
- 聞きたいことを明確にする
- 自分の意見も用意しておく
- 事業や資金について計画を立てる
起業の目的を明確にする
まずは、事業によって何を成し遂げたいのか、起業したい理由や目的を明確にしてください。
事業目的が明確なほど、相手が回答しやすくなり、より最適な答えをもらえます。目的が違えば、回答も違ってくる可能性もあります。
本やネットで下調べをする
人に聞く前に、ひと通りは自分で調べ、最低限の知識は持っておきましょう。起業や経営などについては、本も数多く出版されていますし、ネット上にもたくさんの情報が掲載されています。
ただしネットでの下調べは、情報が間違っていたり、古い情報だったりする可能性もあるので要注意。複数の情報を見る必要があります。
聞きたいことを明確にする

何を相談したいのか、その内容もはっきりさせておいてください。相談者が何を聞きたいかが明確でないと、相手も適切な答えができません。
「起業したいけどアイデアがない」という場合は、少なくとも自分の強みや長所、事業に活かせそうなスキルや資格を洗い出しておきましょう。
自分の意見も用意しておく

相談する事項について、自分なりの考えや希望なども用意しておきましょう。事業を成そうとするなら、まずは自分の考えや意見も持った上で相談すべきです。
自分では何も考えず、ただ答えだけを得ようとする人もいます。しかし、それでは時間を割いてくれる相手にも失礼ですし、自覚や責任感を疑われてしまいます。
事業や資金について計画を立てる

相談前に、自分なりにできる限り事業計画や資金計画を立ててみてください。
起業未経験で事業計画や資金計画を立てるのは難しく、誰かに相談したいと思うのは当然です。
少なくとも事業にどれくらいの資金が必要で、自分はどこまで出せるかをはっきりさせましょう。ある程度までは作ったけれどここがわからない、ここはこういう内容で問題ないか、といった相談の仕方をするのがベターです。
最適な回答を得るための注意点

せっかく相談するなら、自分が納得できる、悩みが解消できる答えが欲しいものです。それには、次の3つの注意点を押さえておきましょう。
- 信頼できる相手を選ぶ
- まずは自分でも調べておく
- 事実を正確に正直に話す
それぞれ見ていきましょう。
信頼できる相談相手を選ぶ
秘密を守って真摯に相談に乗ってくれる、信頼できる相手を選んで相談しましょう。
情報を誰かに漏らすような人や、親身になってくれない人、知識や経験のない人では、有益な回答も期待できません。
すでに起業し、成功している人や、公的な相談窓口、起業や経営に詳しい専門家などに聞くことをおすすめします。
まずは自分でも調べておく
ネットで調べればすぐにわかるようなことを人に相談するのは避けたいところです。相談相手も(チャットボット以外は)人間ですから「本当に起業する気があるのか」「人に頼りすぎでは?」と、応える気力が削がれてしまいます。起業への熱意や姿勢、起業家としての資質も問われます。
まずは自分で考えたり調べたりしましょう。もちろん、ネットの情報も公式なものでなければ古かったり間違ったりしているので、その見極めも必要です。それでもわからなければ相談してみてください。
事実を正確に正直に話す
相談する際は、事実を隠すことなく正直に伝えましょう。見栄を張ったり、隠し事をしたりしてしまうと、最善・最適な答えが得られなくなります。
事実とは異なる答えをした部分が、回答者が答えを出すのに重要だったりするケースはよくあります。その状態でいくら最適なアドバイスをもらっても、うまくはいきません。
相談を活用し、自信をもって起業しよう

起業には不安や疑問がつきものです。経営となるとわからないこともたくさんあるでしょう。専門家などに相談しておけば、不安なく起業が始められます。
無料の相談窓口や専門家な活用して、知識と自信を味方につけましょう。
当サイトを運営する「Bricks&UK」は、税理士法人を中心に、司法書士事務所、社会保険労務士事務所とも連携した中小企業のサポート集団です。
起業や会社設立に関するご相談も無料で承っています。お気軽にご相談ください。
これから起業を考えている方や起業に関する相談相手を探している方は、ぜひ一度Bricks&UKにご相談ください。